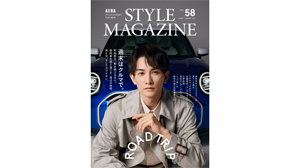「役立つ学問」偏重の果てに 「運命」と諦めた元学徒兵の悔い
太平洋戦争中の1943年10月21日、2万人以上の学生が、雨の東京・明治神宮外苑競技場を行進した。戦況の悪化で徴兵猶予がなくなり、軍隊に送られた「学徒出陣」の壮行会だ。あれから80年。生き残った元学徒兵は未来を奪われたことを悔やみ、研究者は「国の役に立つ学問」を尊ぶ風潮は今に通じると指摘する。
東京帝国大学経済学部の1年生だった町田保さん(99)=山口県柳井市=は、壮行会で行進する学徒の列にいた。
水たまりの中、銃を持って進んだ。ずぶぬれの学生服が肌にまとわりつく。勇壮な音楽に、スタンドで手を振る大勢の女子学生。感極まって、視界がぼやけた。「雰囲気に高揚したんでしょう。無我夢中でした」
戦時下の旧制山口高校を半年繰り上げて卒業し、43年10月1日に大学に入学。学生の徴兵猶予が取り消されたのは、その翌日だった。
「入学したばかりなのになぜ戦争へ」という疑問。そして、壮行会で味わった感動。複雑な気持ちを抱えながら、12月に島根県の陸軍部隊に入隊した。「命令だからしょうがない。運命だ」。そう思うしかなかった。
国の意向に沿う学校を優遇し、「役に立つ学問」だけを奨励する風潮の先に、学徒出陣があった――。記事の後半では、政府と教育の関係を巡り、80年前と現代の共通点を指摘する識者のインタビューを掲載しています。
翌春、久留米第一予備士官学…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら