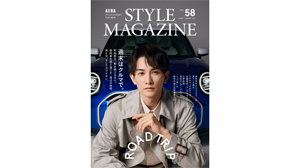性別変更の「生殖不能」手術要件は違憲 静岡家裁支部「必要性欠く」
トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるには、生殖能力を失わせる手術が必要と定めた「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが問われた家事審判で、静岡家裁浜松支部(関口剛弘裁判長)は、規定は「幸福追求権を定めた憲法13条に違反し無効」との判断を示した。11日付の決定で、性別適合手術を受けていない申立人の女性から男性への性別変更を認めた。
申立人側によると、同規定を違憲と判断した司法判断は初とみられる。規定をめぐっては最高裁大法廷が、別の家事審判で近く憲法判断を示す。
申立人は、静岡県浜松市の鈴木げんさん(48)。出生時の性別は女性だが、40歳で性同一性障害と診断され、男性ホルモンの投与や乳房の切除を行い、男性として暮らす。
生殖能力を失わせる規定について「性自認の通り性別を尊重される権利、身体が侵襲されない権利を侵害し、違憲だ」と主張し、卵巣切除などの手術なしでの性別変更を求めていた。
「社会的な混乱は限定的」
家裁は、性別変更は「切実な法的利益」だが、規定の存在で「手術を受けざるを得ず、意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約される」と指摘した。
規定は「女性から男性に性別変更した人が出産する」といったケースが起きれば社会が混乱するとして設けられた。家裁は、性別を変更する人が変更前の性別の生殖機能で出産すること自体がまれで、「混乱といっても相当限られる」と述べた。
さらに生殖不能要件を撤廃する国際的な流れや、国内での施策の進展にも言及。その上で、手術による「人権制約の重大さ」に比べ、社会的混乱の防止を目的とする規定は「もはや必要性、合理性を欠くに至っている」と結論づけた。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら