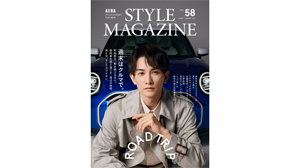子どもは読書しなくなった? 東京都調査「家に本がある」に顕著な差
データで読む東京都の教育⑪
東京の子どもたちは本を読まなくなっているのか。東京都教委のデータをもとに、教育政策が専門で、発展途上国で読書支援や教育データ分析に携わる学習支援NPOの畠山勝太理事(38)に尋ねると、別の調査結果の重要性を指摘されました。貧富や環境の差が読書の差につながっている――。詳しく聞きました。
◇
読書は全ての学力の基礎になります。読解力はもちろん、数学や理科も伸びます。
世界銀行と国連児童基金(ユニセフ)の職員として約10年にわたり、アフリカのジンバブエやマラウイなどで、その国の教育計画の策定支援や教育データの分析に従事し、貧しい子どもたちの学習を支援するNPO「サルタック・ジャパン」理事としてネパールで読書支援も続けています。「平和構築のための幼児教育支援の産学官連携について」というテーマで、内閣府の国際平和協力研究員も務めています。
現地での活動や、米国や発展途上国での研究データから、読書の力を実感しています。特に貧困層や低年齢に効果があります。
東京の子どもたちは、どうでしょうか。
都教委の子供読書活動推進に関する調査(昨年度)によると、調査時から直近の1カ月間に本を読んでいない児童・生徒は小2で4・4%(2019年度は2・9%)▽小5で5・1%(4・2%)▽中2で10・3%(9・9%)▽高2で33・4%(30・6%)と、「いずれの学年も2019年度に比べて割合が増加した」と、この調査の概要版に記述があります。
しかし、サンプル調査なのに前回と統計的に有意に変化したのかの記述は無く、ポイント差が大きくないことなどから、統計的に有意な変化といえるのかは慎重に判断する必要があると考えます。あまり変化がなかった、と見るのが無難でしょう。
埋もれていたデータ
むしろ一番の肝といえる調査結果が、報告書の中に埋もれていました。
それは、家庭環境など「あて…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
【調査分析に研究者の力を】 「物理的、文化的な差が本を読む機会に影響している。本を巡る家庭環境の差が読書の格差、ひいては学力の格差へとつながると言えます」と畠山さん。 文部科学省の全国学力調査は子どもたちに、家に本が何冊あるかを本棚のイラ
…続きを読む