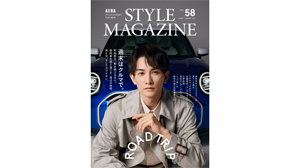ぬれた古文書を修復、デジタル保存も 市民に広がる歴史資料の救い手
現場へ! 歴史資料を守る②
阪神・淡路大震災を機に、神戸に生まれた歴史資料ネットワーク。それから約30年、被災資料の救い手は全国に、そして市民の間に広がっています。
部屋の中で、7人のボランティアが黙々と作業を続けていた。水につかり、くっついてひとかたまりになってしまった冊子のページを、一枚一枚丁寧にはがしていく。まとめ役の森多毅夫さん(69)が「これは土地関係の覚書。1冊の作業を終えるのに、数カ月かかることもあります」と説明してくれた。
長野市の川中島古戦場史跡公園内にある市立博物館。2019年に長野県内に大きな被害をもたらした台風19号を機に設立された「ながはくパートナー 文化財保存グループ」は、ここを拠点に週2回、被災した歴史資料の泥やカビなどを落とす応急処置を行っている。
中心になっているのは市民ボランティアだ。県内で同様の活動を行う信州資料ネットなどの協力を得ながら、これまでに地元の寺の経典や地域の古文書など、数千点の作業を終えた。処置を終えた資料は元の所蔵先に返す。ただ、カビを防ぐために一時的に凍らせたままの資料は、大型据え置き冷凍庫に三つ分もあるという。「いつ終わるか、正直まったく読めません」
地震や津波などの災害で被災…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら