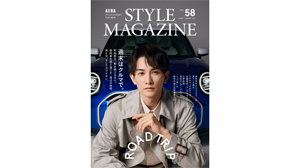LGBT法案、目的はどこへ? 行政法学者が見た問題点
「LGBT理解増進法案」をめぐり、文言の修正や削除をしたり、追加したりする動きがあった。こうした法案で、性的少数者への理解を広げるという本来の目的が達成できるのだろうか。提出過程で出ていた3案について、日本大学大学院の鈴木秀洋教授(行政法・地方自治法)に聞いた。
◇
行政法学者であり、元自治体職員として条例の制定を担当した経験から、現在の「LGBT理解増進法案」の提出過程の報道に驚いている。
まずこの法案は、学校でのいじめや就職時における差別、職場での差別的取り扱いを解消するのが目的だったはずだが、その目的があいまいになってしまった。
実際に学校の現場などで、「男らしさ」「女らしさ」の基準から外れる子どもが虐待や指導を受けるといった事例がある。
本来、こうしたエビデンス(根拠)を立法事実として、その解決のために目的や基本理念を掲げ、国や地方自治体の役割などを定めるのが法律だ。一つの法律が、全ての問題を解決するわけではない。
現在、トランスジェンダーのトイレ利用に関する極端な事例の議論が散見されている。問題があるなら、公衆トイレの設置や利用についての個別具体的な法律の制定や指針などで対処するべきだ。
利用者の様々な不安や心配を…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
LGBT理解増進法案を巡っては既に専門家や当事者団体らからその法案の問題点について様々な指摘が上がっています。とりわけ原案の「性自認」は、ジェンダーレストイレやトランスジェンダーのトイレ利用に関する極端な利用の可能性を背景に、与党修正案では
…続きを読む