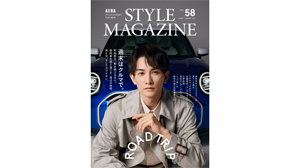「無関心な多数派」だった私、変わった一歩 同性婚が実現しない日本
広島で19日から開かれる主要7カ国首脳会議(G7サミット)を前に、朝日新聞が日本以外のG7各国の在日大使館に行ったアンケートからは、同性婚や性的少数者(LGBTQなど)の人権擁護の促進に前向きな姿が浮かび上がりました。日本との違いは、どこから生まれるのでしょうか。公益社団法人「Marriage For All Japan―結婚の自由をすべての人に」代表理事で、弁護士の寺原真希子さんに聞きました。
同性婚の法制化などに向けて活動を続ける寺原真希子さんに、日本におけるハードルが何なのか、尋ねました。記事後半では、寺原さんが性的少数者の人権問題に取り組むようになったきかっけについても聞いています。
――日本以外のG7の国の多くは、性的少数者の人権擁護に積極的です。一方、日本では同性婚が法制化されず、差別禁止法もありません。この違いはどこから生まれていると思いますか。
根源的には、「人権」に対する感覚が不足しているのだと思います。性的少数者の問題に限らず、いまの日本では、少数者の「人権」は、多数派、それも国会の中の多数派が守ろうとしなければ守られない状況に陥っています。
そこでは、民主主義の捉え方に誤解があるように思います。「多数派が賛成しない限り法制度が変わらないのが民主主義というもの」と理解している人が国会議員にもいらっしゃるようですが、その理解は誤りです。そのような理解に立つと、少数者への人権侵害はいつまでも解消されないことになってしまいます。
米国で連邦最高裁が同性婚を禁止する州法を違憲とした判決でも言及されていましたが、民主主義が適切なのは、個人の基本的権利を侵害しない限りにおいてであって、民主主義は、多数派が少数派の人権を侵害することを正当化する概念ではありません。特に政府がそのことを正確に認識したうえで、一人ひとりの基本的権利が保障されるよう、法整備を進める必要があります。
――日本以外のG7の国からの回答の中で、気になる点はありますか。
ドイツの「より包括的で受容的な社会は、前向きな変化と見られている」という回答です。
同性婚などの性的少数者の人権を保障するための法整備は、性的少数者自身が自分らしく生きやすくなることはもちろん、その家族・友人・同僚・地域の人たちなど、周りの人々にとっても前向きな変化を与えます。
また、ある事柄や場面で多数派である人も、他の事柄や場面では少数派となりえます。少数者の生き方を尊重する社会は、すべての人が生きやすい社会を意味するといえます。
昨年11月30日、同性カップルが「家族になる法制度」がないのは違憲(状態)とした東京地裁判決も、そのような法制度を整備することは「社会的基盤を強化し、異性愛者を含む社会全体の安定につながる」と明確に述べています。
賛成率7割超の日本で、なぜ
――朝日新聞が2月に行った世論調査では、72%の人が同性婚を認めるべきだと答えました。にもかかわらず、法制化にいたらない現状をどう捉えていますか。
海外で同性婚が法制化される前と後を比べると、後の方が賛成率が上がる傾向にあります。例えば台湾では、法制化前の2018年の調査における賛成率は37%でしたが、法制化から3年後の22年の調査では60%に上がりました。今の日本の賛成率は、同性婚法制化前であるにもかかわらず、法制化後の台湾における賛成率よりも高いのです。
海外と比較しても賛成率が極…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
台湾で「法制化前の37%から法制化後には60%まで賛成率が上がった」という点が興味深いです。 知らないからこそ恐れていたが、実際に同性婚が身近になってみると何も怖がることはないと多くの人が気づいた、ということでしょう。 私たちは皆「知らない
…続きを読む