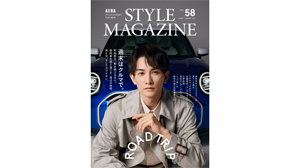パートナーシップ宣誓制度導入で一歩前進
LGBTQなど性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を栃木県が9月から導入した。県内7市町も同様の制度を採り入れており、県によると、11月末までに計15組が宣誓した。
「栃木すごいね。あたし好きになっちゃった。東京でも、やっとこないだですよ」。11月上旬に宇都宮市で開かれた性の多様性に関する催しで、2002年に性同一性障害を公表して16年に性別適合手術を受けたタレントのKABA.ちゃんが、県の導入についてそう話すと、120人以上の参加者から拍手が起きた。
私が宇都宮に赴任したのは19年春。同年6月には、県内で初めて制度を導入した鹿沼市を取材した。
制度では、パートナー同士の公営住宅への入居や病院での面会などが可能になり、家族同様の行政サービスが受けられるようになった。しかし、民法や戸籍法は同性婚を認めていない。宣誓制度は同性婚とは違って法的効力がなく、相続や共同親権、税の配偶者控除などは受けられない。
宇都宮大学の公認サークル「LGBTs研究会 にじみや」に所属するシマさん(19)=仮名=は、自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」だ。出身の東北地方では性的少数者への理解は進んでいないと感じる。
宣誓制度については「少しずつ浸透しており、地方でも必要だと思い始めているのだろう。周りの目もあり、最初はどうしても批判的な声も出るが、何年かすれば当たり前のことになるのでは。進めることが大事」と話した。
日光市の奥山瑞明さん(50)は、市が昨年9月から導入したパートナーシップ宣誓制度の第1号だ。パートナーはカナダ人男性で、19年にカナダから2人で移住した。カナダで結婚していても日本では同性婚は認められていないため配偶者ビザを手にすることができず、毎年ビザを更新しないといけない。宣誓制度について「一歩前進だが、将来は同性婚が法的に認められてほしい」と訴えた。
県は今月20日、宣誓制度を導入している隣県の茨城、群馬と連携協定を結んだ。3県のどこかで宣誓の手続きをした人は、隣県に引っ越しても簡単な手続きでこれまでと同様のサービスを受けられるようになる。
制度を初めて導入したのは東京都渋谷区と世田谷区。2015年のことだ。私は14年から4年近く、ネットメディアのハフポスト日本版(東京)に出向し、LGBTQに関心の高い若い編集者らと仕事をした。東京で今も活躍する当事者とLGBTQの企画を立てたり、取材をしたりした。
当時は「都会の話」と思っていたが、決してそんなことはない。同性カップルの婚姻保障が一日も早く実現することを願う。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら