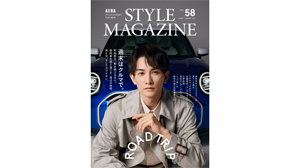栃木県もパートナーシップ宣誓制度を導入 一歩前進も課題は…
栃木県は9月から性的少数者カップルに公的証明書を発行する「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。県内では7市町が同様の制度を採り入れ、多様性を認め合う共生社会の実現に少しずつ近づいている。日光市の制度第1号となったカップルを訪ねた。
英会話教室の看板が立つ日光市の一軒家。広い庭には手入れされた木々が生い茂る。同市が昨年9月から導入したパートナーシップ宣誓制度の第1号である奥山瑞明さん(49)と、カナダ人のデビッド・ハメルさん(49)の自宅だ。
「日本に来て彼には不安もあったが、証明書を手にして精神的に落ち着いてきました。ただ、ビザのために山のような書類を用意しないといけない」
奥山さんはそう話す。カナダで結婚していても日本では同性婚は法的に認められておらず、配偶者ビザを手にすることができない。ハメルさんは自宅で英会話教室を開いているが、毎年、ビザを更新する必要がある。
奥山さんは川崎市などで少年時代を過ごし、高校時代に男性と交際した。19歳の時、恋愛対象が男性だと家族に告白した。中国の大学を卒業して帰国した。26歳の時、母親に強く懇願されて仕方なく女性と結婚したが、2年で離婚した。
2002年にカナダに留学した。現地でハメルさんと知り合い、一緒に住み始め、10年に結婚した。ハメルさんは、異国暮らしで苦労してきた奥山さんの姿を見てきた。「カナダで暮らし続けるのはあなたにとって不公平」と、日本に移り住むことを提案した。
日光市を観光で訪れて気に入り、19年に移住した。同市が宣誓制度を導入した直後に同性カップルであることを公表した。
「自分たちのことをルームメート同士だと思っていた近所の人たちが、『おめでとう』と優しく接してくれた。うれしかったです。同じような立場の人たちを勇気づけたいとも思っています」
奥山さんは宇都宮市内に1店、カナダに5店の飲食店を経営している。中国にあった店はコロナ禍で閉店を余儀なくされるなど、すべてが順調というわけではないが、充実した日々を過ごしている。
奥山さんが心配するのは将来のことだ。宣誓制度は同性婚とは違って法的効力がなく、ハメルさんには相続や税の控除などの権利がない。
「来日したときに制度を設けるように市役所にお願いに行きました。そこから考えると一歩前進。10年かかるかもしれないけれど、同性婚が法的に認められてほしい」
◇
制度はLGBTなどの性的少数者のカップルを公認するもの。パートナー同士の公営住宅への入居や病院での面会が可能になるほか、新婚世帯らが協賛店舗の割引などの特典を受けられる「とちぎ結婚応援カード」(とちマリ)の利用など、家族と同様の行政サービスが受けられる。
県人権施策推進室によると、9月末までにいずれも宇都宮市に住む3組のカップルが宣誓した。県のほか、2019年6月に導入した鹿沼市を始め、県内では栃木、日光、野木、佐野、大田原、那須塩原の7市町が同様の制度を導入し、各市町で9月末までに計9組が宣誓している。
茨城や群馬など宣誓制度を導入している県はほかにもあるが、他県から引っ越してくると、改めて宣誓をやり直さないといけない。栃木県は他県との連携を検討している。また、イベントを開くなどして、県民への制度の周知や性的少数者への理解促進、差別解消を図る。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら