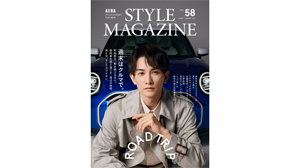「パートナー制度があればいい」は危険な考え 三成美保教授が警鐘
400を超える自治体が性的少数者のカップルに公的な証明書を発行する「パートナーシップ宣誓制度」を導入する一方で、自治体ごとに制度の使いやすさや内容に違いが生まれている。
今後、性的少数者をめぐる制度設計や改良について、自治体や国はどう向き合うべきなのか。ジェンダー法学者の三成美保・追手門学院大学教授に聞いた。
――香川県のパートナーシップ制度について、当事者から疑問の声が出ています。
内容を見ると、不十分である印象を受けます。
当事者にとって、パートナーシップ宣誓制度を利用することは、部分的にとはいえ、自分の性的指向をカミングアウトすることです。一種のリスクがある行為と言えるでしょう。
しかし、香川県の制度の場合、そのリスクに見合ったリターンが得られません。利用者も限られてしまいます。
――都道府県や市町村において、性的少数者に向けた政策立案や制度設計はどのように考えるべきでしょうか。
三成さんはパートナーシップ宣誓制度の広まりを評価する一方、「制度があればいい」との考えに警鐘を鳴らしています。後半で詳しく紹介します。
現状、各自治体のパートナー…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
パートナーシップ宣誓制度が「あればいい」わけでないのはその通りだと私も常々思っています。 制度があることによって、一種の教育的効果や当事者へのエンパワーメントにはなるだろうけれど、法的な効果が付与されておらず、それでは法的保障を求める人た
…続きを読む