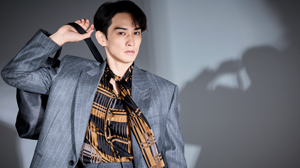「国際法違反」と断じた原爆裁判 「虎に翼」モデルの裁判官も担当
被爆者らが期待してきた核兵器禁止条約への参加がかなわぬまま、広島選出の岸田文雄首相が退任する。来年3月にある第3回締約国会議へのオブザーバー参加も拒否するなど日本は条約に背を向けたままだが、核兵器は「国際法違反」と初めて指摘した裁判が、半世紀余り前の日本であった。中東や欧州で核兵器使用の危機をはらむ紛争が続く中、この判決の意義に光を当てようとする人もいる。
1955年4月、広島と長崎の被爆者5人が日本政府に賠償を求めて裁判を起こした。
日本の戦争犯罪は戦後、戦勝国側による極東国際軍事裁判(東京裁判)で裁かれた。だが、米国による原爆投下の責任は問われることのないまま、サンフランシスコ講和条約が52年に発効。その翌年から大阪の岡本尚一弁護士(1891~1958)が訴訟を呼びかけ、協力者を探した。
原告となったのは、妻子5人を原爆で失った人、両親を亡くし生活に困窮する子ども、腎臓や肝臓に障害を負い働けない人ら。「悲痛極まる精神的苦痛」「名状し難き苦悩」などと被害を訴えた。日本の裁判所に米国政府を裁く権限はないため、日本政府に賠償を求めるほかなかった。
政府が棄却を求める中、原告側が最大の争点にしたのは、原爆投下は国際法違反かだ。「人類社会の安全と発達とを志向希求する国際法と到底相いれない」と主張した。
原告は、原爆がもたらす残虐な被害の立証を積み重ねる。爆風による破壊、熱線によるやけどや火災、そして、放射線による原爆症。「加害影響力は、旧来の高性能爆弾に比べて著しく大きく、しかも不必要な苦痛を与える」と訴えた。
判決は、こうした原告の訴え…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら