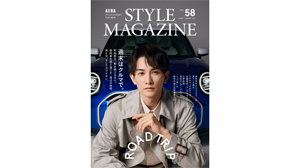かつて「アナログ」とは時計だった 辞書編纂者も悩む、言葉の微妙さ
「アナログ」と「デジタル」。この二つのカタカナ語を日常会話の中で気軽に使っていませんか。でもふと考えれば、そもそも何を意味し、いつごろから人々に使われ始めたのでしょう。「三省堂国語辞典」編纂(へんさん)者で、日本語学者の飯間浩明さんに聞いてみました。
――そもそもアナログ、デジタルはいつごろから一般に広まった言葉なのですか。
「外来語としては、すでに1950年代に『デジタルコンピューター』『アナログコンピューター』と使われています。ただ、広く使われるようになったのは、70年代ごろに、数字で時刻を表示する『デジタル時計』が広まったことがきっかけです。それまでの、長針と短針で時刻を示す時計を『アナログ時計』と呼んで区別をすることになりました。デジタル時計が誕生しなければ『アナログ時計』という言葉は必要なかったわけです」
――「言葉が必要ない」とは?
「似た例を挙げましょう。今で言う和服は、昔はただ『服』と呼んでいました。そのうち洋服が生活の場に現れたので、それまでの着物の服を区別する必要が生まれ、『和服』と名づけられました」
「新しいものが登場したとき、以前からあったものをそれと区別するため、改めて命名し直すことがあります。レトロニムと言われるものです。『デジタル時計』に対する『アナログ時計』も、レトロニムの一種です。『アナログ』と言えば、一般的にはアナログ時計を意味した時代がしばらく続きました」
2014年版まで変わらなかった辞書の語釈
――必ずしも時計を指し示さなくなったのはいつごろでしょうか。
「80年代以降、意味が次第…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら