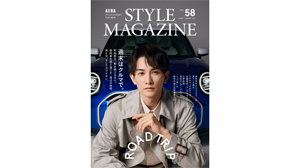教育現場の保守支配 政治学者が読み解く、君が代を歌わせたい論理
入学式や卒業式で、自らの思想から君が代を歌えない、起立できない、という公立学校の教員たちが大量に処分されてきたが、その強制の背景に何があったのか。政治学者の中野晃一・上智大教授は、この20年余りで進んできた「保守支配の再構築」が教育現場に浸透していると指摘する。
◇
国旗・国歌法が成立した1999年は、日本政治の転換期でした。当時の小渕政権は、民主党を潜在的な対抗勢力とみなし、くさびを打ちこもうとしました。周辺事態法を含めた新ガイドライン関連法などを次々に成立させていきます。その一つが国旗・国歌法で、対応をめぐって民主党内は分断されました。
一方、国旗・国歌法の制定過程で、野中広務・官房長官(当時)が、「法制化するとしても、掲揚や斉唱を強制するものではない」と答弁したことに表れているように、自民党が穏健な保守だった最後の時期でした。やがて小泉政権が誕生し、自公連立の枠組みのもと、「保守支配」の再構築の過程へと入っていきます。2000年代に入り、日の丸・君が代をめぐり教員たちが大量処分されていくのも、これと軌を一にしています。
職務命令の問題にすり替えられた政治的論争
保守支配の再構築の特徴の一…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」。 これは、テキサス州でグレゴリー・リー・ジョンソンによる国旗旗焼却行為に対し、崇敬の対象と
…続きを読む