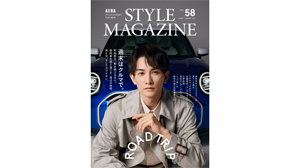「馬鹿者が」 どん底の抵抗に見る次の時代 ブレイディみかこさん
ブレイディみかこさんの「欧州季評」(最終回)
「要は経済なのだよ、馬鹿者が」
これは、1992年の米大統領選でクリントン元大統領の陣営が使った有名な言葉だ。ちなみに、この連載が始まったのは、それから四半世紀が過ぎた2017年。だが、この5年間、わたしは欧州季評を書きながら幾度となくこの言葉を思い出したのだった。クリントン元大統領は選挙で勝つための標語としてこの言葉を使ったし、わたしも左派が支持を伸ばすために「要は経済」の姿勢が肝要だと信じていた。だが、そういう呑気(のんき)な時代は終わった。「生活費危機」が広がる英国では、この言葉はもはや戦略ではなく切実な現実だ。
この年末年始、少なくともわたしの周囲には浮ついたムードはなかった。わたしの友人や知人には、コロナ禍中にいわゆる「キー・ワーカー」と呼ばれた人々が多い。彼らにとってこの冬は「ストライキの季節」だ。看護師、救急隊員などの医療従事者、鉄道職員、郵便職員、高等教育の教職員、空港の入国審査官や税関職員など、続々とストの輪が広がっている。「今年はクリスマス・ショッピングよりピケットラインに立つ」と言った知人もいた。
彼らだって好きこのんでストをしているわけではない。看護師の友人も最後までストに参加するか悩んでいた。人の命を預かる職業の人間が、自分の事情でストなんかするわけにはいかないという責任を感じていたのだ。だけどシングルマザーの彼女には、食卓に子どもたちの食事を載せる義務もある。罪悪感に苦しみながら、それでも、ギリギリのところで決断し、彼女はストに参加した。そんな心情を庶民も理解しているのだろう。看護師のストライキを64%の人々が支持しているという調査結果もあったとBBCは報じていた。
物価高と光熱費の高騰、欧州連合(EU)離脱の影響で現在の状況になっているのは明らかだが、英国の場合、2010年に政権を握った保守党の緊縮財政のせいでその前から貧困と庶民の不満は広がっていた。
ホームレスが急増したこと…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら
- 【視点】
ブレイディさんの「欧州季評」からは毎回、社会に対する喜怒哀楽のアンテナを磨いてもらっていました。「貧困は人権の問題なのである」という最終回のメッセージが多くの方に届いてほしいと願いつつ、ピンと来ない人も少なくないのではと暗い気持ちになりま
…続きを読む