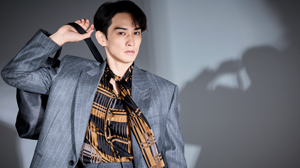第8回フリードマン・ドクトリンの結末 ボーイングは株主をも食いつぶした
いまから半世紀ほど前、アメリカ産業界のトップ企業だった自動車メーカー、ゼネラル・モーターズ(GM)を安全・品質問題で追い詰める30代の弁護士がいた。
のちに米大統領選にも出馬する著名消費者運動家、ラルフ・ネーダーの若き日だ。著書「どんなスピードでも自動車は危険だ」がベストセラーとなり、志を同じくする弁護士らがGM株を買い集めて株主総会に出席。「公益代表」の取締役を選任したり、安全や環境問題に取り組む委員会を設けたりするよう、GMに迫っていた。
米経済学者ミルトン・フリードマンがそのころ記したエッセー「企業の社会的責任とは、利益を増やすこと」(ニューヨーク・タイムズ・マガジン、1970年9月13日号)は、GMに社会的責任を果たすよう求めたネーダーらの運動に対抗する文脈で生まれたものだ。
「株主の利益こそすべて」
企業はお金もうけに集中すべきで、社会的な問題は慈善団体や政府に任せた方がうまくいく――。「フリードマン・ドクトリン(教義)」と銘打たれたそのエッセーは、以来半世紀にわたり米国や西側世界を席巻した新自由主義や株主資本主義の、「のろし」ともいえる記念碑的な一文となった。
米金融大手シティグループの元最高経営責任者(CEO)、ジョン・リードが銀行業界で仕事を始めたのは60年代にさかのぼる。そのころ、銀行にとっての利益とは「1年間顧客の役に立つ良い仕事をして、その結果として手元に残っているもの」だったという。
しかし、70年代を境に価値観の転換が起きる。「株主の利益こそすべてであり、経営者の報酬も株主利益に連動すべきだという考え方は、まずは金融業界を支配した。それが徐々に、幅広い民間部門へと浸透していった」とリードは振り返る。フリードマンの思想は、制度や判例、慣行として米経済社会に根を張っていった。
その株主資本主義を体現する企業となったボーイングが起こした、小型機737MAXの連続墜落事故。2機目となったエチオピア航空機の犠牲者のなかに、米ワシントン在住で国際公衆衛生に取り組んでいた24歳のNPOスタッフがいた。サムヤ・ストゥモ。あのラルフ・ネーダーの大姪(おおめい)だった。
「日本の法律に米国も学べ」
事故後、朝日新聞の電話取材…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら