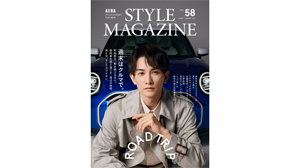未成年の子がいると性別変更できない? 最高裁判事1人が違憲判断
10歳の娘がいる兵庫県の会社員(54)が戸籍上の性別変更を求めた家事審判で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は会社員の訴えを退けた。戸籍変更を認める性同一性障害特例法が設けた「未成年の子どもがいないこと」という要件の違憲性が争点となったが、合憲とする初判断を示した。裁判官5人のうち4人の多数意見で、1人が違憲とした。
会社員は幼少期から自身の男性の体に違和感を持ち、成人した頃からホルモン治療を始めた。親の勧めで女性と結婚し、娘が生まれた後に離婚。2019年に性別適合手術で女性の体になり、神戸家裁尼崎支部に性別変更を求めた。
04年施行の特例法上、性別変更には①20歳以上②独身③子どもがいない④手術で精巣・卵巣を摘出⑤変更後の性別の性器に近い外観を備える――という要件を満たし、医師2人の診断書を添えて家裁に申し立てる必要がある。要件は社会や子の混乱を防ぐためなどとされ、08年の改正で③は未成年の子に緩和された。
会社員は③の要件だけ満たせず、この要件は幸福追求権を保障した憲法13条や法の下の平等を定めた憲法14条に反すると主張。だが、家裁も大阪高裁も「家族秩序や子の混乱を避けるという合理性がある」と退けたため特別抗告した。
11月30日の最高裁決定で多数意見は、改正前の子なし要件を同様の論理で合憲とした裁判をふまえ「憲法に反しないことは判例の趣旨に徴(ちょう)して(照らして)明らか」とだけ述べた。
違憲とする反対意見を書いた学者出身の宇賀克也裁判官は、「未成年だから混乱する」という理屈は抽象的で、同様の要件は世界的にも異例だと指摘。戸籍を外見に合わせられず就労などで支障が出れば「かえって子の福祉を害する」と述べ、憲法13条が保障する「自己同一性を保持する権利」を侵害するとした。
1万人超す申し立て、専門家「法を見直して」
「心と体を変えても戸籍を変…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら