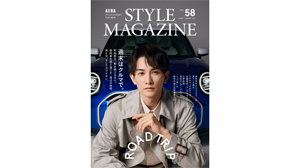第1回オードリー・タンを生んだ社会とは 同性愛者の私が感じた日本との差
台湾からのヒント オードリー・タンを育んだ社会①
台湾で天才と称される、40歳のデジタル担当相オードリー・タン氏は、昨年からのコロナ禍でその能力を発揮し、危機を救ってきた。こうした人材が力を発揮できるのは、ガラス張りの行政の実現に取り組み、多様性を尊重し、女性や若者の政治参加が盛んな社会の「包容力」ゆえだ。これらを台湾はどう育んだのか。世の中はどう変わったのか。タン氏の言葉をヒントに、台湾の歩みをたどる。そこから、日本の現在地もまた、みえてくる。
オードリー・タン氏の言葉
私は12歳で初めてネットの世界に飛び込んだ時、特に自分の性別を強調しませんでした。ネット上では自身の価値観とどんな貢献ができるかが大切だと知った後、性別を意識したことはありません。私は14~15歳と24~25歳で2度の思春期を経験しました。比較的容易に異なる性別の人のことを理解できると思っています。性別は世界と接する際に自らが示している一面に過ぎません。大切なのは、自分と異なる相手やその経験、価値観をいかに受け入れるかです(多様化した社会をめざす催しでのあいさつで)
台湾は2年余り前に、アジアで初めて、同性婚を法律で認めた。世論には当時、日本と同じく反対の声も強かった。どうやって実現させたのだろうか。
台湾に移住した日本人「強い自己肯定感を持てた」
台湾最南端の屛東県に住む日本語教師の有吉英三郎さん(42)には忘れられない光景がある。
台湾で同性婚を認めないのは憲法違反だとする初めての憲法判断が出た、2017年5月のことだ。立法院(国会)の前に集まった数百人の同性愛者が、うれし涙を流しながら抱き合っていた。友人と現場にいた有吉さんは、日本で家族や親しい友人以外には自分が同性愛者だと明かせなかった日々を思い出し、「強い自己肯定感を持つことができました」と振り返る。
有吉さんは36歳だった15年8月、台湾に移住するつもりで、留学生活を始めた。それまで何度か旅行で訪れ、多様な人々を受け入れる社会の包容力を感じ、ひかれた。「同性愛者として、日本で感じてきた息苦しさを一生背負いたくはなかったんです。だから、台湾では必ず自然体で過ごそうと自分に誓いを立てました」
幼い頃から、自身が男性に興味を抱くことに気づいていた。家族に告白できたのは22歳の時。ただ、大学を出て日本で勤めた学習塾では私生活を話すことを避け続けた。教え子の保護者から「有吉先生は結婚しないの?」と尋ねられるたびに答えに窮した。3年間ともに働き、退職する同僚講師から「有吉さんは、一度も自分の話をしてくれませんでしたね」と残念がられたこともある。
有吉さんは「ありのままの自分を受け入れて欲しいと思う気持ちがある一方、相手との関係など、大切だと感じているものを失うことが怖かったんです」。そして、こう付け加えた。「同性愛者は周囲の人の言動を詳細に観察しています。同性愛者に対して、どんな考え方を持っているのかを判断するためです。だから、同性愛者への理解がある人は、普段から積極的にそのことを発信して欲しい。私たちはその言葉に安心して話し出せるのです」
台湾で暮らし始めて3カ月が経ったころ、現在のパートナーで心理カウンセラーの盧盈任さん(33)と知り合った。交際を始め、毎年1回、盧さんを伴って日本に戻るようになると、日台の差を痛感した。
帰国中に、普段通り手をつな…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら