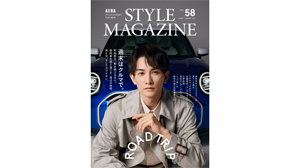「男性支配に嫌だという権利がある」憲法24条の意義は
憲法には男女の平等がうたわれているのに、実現はいまだ遠い。ジェンダー平等における憲法の果たす意義について、静岡大学の笹沼弘志教授に聞いた。
――コロナ禍で仕事を失って困窮したり、家族内の暴力に苦しんだり、女性を取り巻く深刻さが浮き彫りになりました。憲法は理想にすぎないのでしょうか。
「憲法24条には、『法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない』とあります。これは、家庭の中の支配や差別が起きないように、国家が介入をしなければならない、ということです。しかし、24条のそうした意味について、これまで憲法学者の間でも注目されてきませんでしたし、国の是正も不十分です」
《第24条》
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
――家庭の中の平等のために、国が是正するとはどういうことでしょうか。
「24条は、嫌なことは嫌だと言っていい権利なのです。たとえ夫に養われていても、夫の理不尽な支配が嫌なら逃れていい。逃れた人にも、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために25条がある。知識や技術を身につけるための教育を受ける権利として26条があり、働く権利として27条があるのです。よく25条が生活保護の根拠として言われますが、25条だけがセーフティーネットなのではなく、すべての人の幸福追求権を保障するために24、25、26、27条があるのです」
《第25条》
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
《第26条》
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
《第27条》
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
――憲法の中で、24条がこの順番にある、つまり、25、26、27条の前にあることに意味があるということでしょうか。
「24条の起草過程に注目すると、それがよくわかります。憲法には、国家からの自由を保障する『自由権』と、国家の介入によって権利を保障する『社会権』がありますが、24条は社会権の先頭に位置づけられています。そして、GHQで関わったベアテ・シロタ・ゴードンさんの草案には、『親の強制』や『男性の支配』を否定して、初めて『個人の尊厳』と『両性の本質的平等』が保障されると書かれていました。それを読んだとき、目が飛び出るほど驚きました」
――目が飛び出るほど? なぜでしょう。
「実際の24条には、『男性…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら