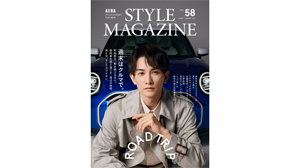法の番人の退任劇、いま明かす 車中で後任は黙り込んだ
自らの考えに近い人物を置くことで政策を実現する――。安倍政権の7年8カ月は、「人事慣行」を破ることで、法治のありようまでを変えうることを示した。象徴的だったのが、安保法制の制定を目指し、「法の番人」といわれる内閣法制局長官を退任させた人事だった。山本庸幸さん(71)が見た、その政治手法の本質とは。
――2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使の小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか。
「6月ごろでしたか、事務担当の官房副長官の杉田和博さんから閣議後に『7月21日の参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」
――法制局経験がなく、外務省出身の小松氏が就任すれば、法務、財務、経済産業、総務の4省出身者が交代で、次長から昇格する長年の人事慣行が破られるからですね。どう受け止めましたか。
「安倍晋三首相の集団的自衛権行使への思いがそれだけ強いのか、と改めて感じました」
自分が退任後、すぐに動いた
――山本さんは、集団的自衛権の行使を容認するために憲法9条の解釈を変更することは「従来通りできない」と拒否してきました。安倍首相(当時)から、それまでに、この問題について何か指示されたことはあったのですか。
「第1次安倍内閣の時、内閣法制局第1部長として、当時の長官と共に安倍首相に集団的自衛権行使と憲法の関係に関する政府の当時の法解釈をご説明に行ったことがありました。しかし、安倍首相はただうなずいて淡々と聞いているだけで、説明の後、何も具体的指示や議論はありませんでした」
――どう思いましたか。
「その時は、集団的自衛権行…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら