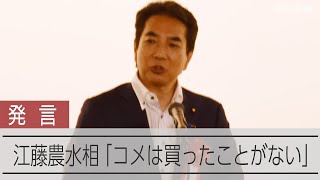(社説)契約の電子化 消費者保護に逆行する
消費者保護を図るための法改正なのに、新たな被害を生んでしまっては元も子もない。本来の趣旨に立ち返り、正すべき点をしっかり正すのが、法案を審議する国会の責務だ。
訪問・電話勧誘販売やマルチ商法などの規制を強化する特定商取引法の改正をめぐって、与野党が対立している。
政府が提出した改正案の内容は大筋で評価できる。問題になっているのは、消費者と業者が取り交わす契約書面を、消費者の承諾を条件に、電子メールなどで交付できるようにすることの是非だ。法案はすでに衆院を通過しているが、認識が深まるにつれ、参院で野党の間に反対論が広がってきた。
商品を購入して預けてもらえれば、別の客に貸し出して、その代金を配当する。そう言って品物を売りつける「販売預託商法」を原則として禁止する預託法改正案にも、同様の規定が盛り込まれている。
電子化は時代の流れだが、紙に比べて内容の点検がおろそかになりがちで、手元に実物が残らない欠点もかかえる。
昨秋、延べ1万人が2千億円超の詐欺被害を受けたジャパンライフ事件が摘発されたが、契約書面があったため、弁護士や消費生活相談員が不当な内容に気づくことができた。これがメールでもよいとなれば、察知が遅れたり被害立証が難しくなったりすることが考えられる。
条件となっている「消費者の承諾」も、お年寄りをはじめ、ネット利用に不慣れな人が業者に誘導されて安易に与えてしまう恐れがあり、有効な歯止めになるか疑問だ。
そもそも消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護の後退になるとして応じてこなかった。今回の法改正にあたり、昨夏まで検討を重ねた同庁の有識者会議でも議題になっていなかった。
ところが、デジタル化推進の旗を掲げる菅政権が発足し、オンライン英会話学校の要望を受けた政府の規制改革推進会議が同庁に検討を求めると、一転して容認。さらに「法的整合性」を理由に、販売方法を問わず解禁に踏み切った。拙速・乱暴というほかない。
政府は、法成立後に政省令を定めて被害が出ないように工夫するというが、行政任せの危うさはこの間の経緯を見ても明らかだ。逆に縛りすぎれば、利便性を損なうことにもなる。
問題の箇所を削除したうえで法案を成立させ、消費者団体や弁護士会などの意見も反映した法規制のあり方を慎重に探るべきだ。デジタル化の名の下、つけが消費者に回るような事態は避けなければならない。