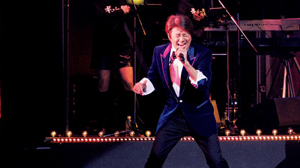(EYE モニターの目)今月のテーマ:緊急事態宣言をめぐる報道
■より生活に近い記事を
緊急事態宣言が出るまでの経緯についての内容が多い。家庭内感染が増えているのにもかかわらず、メディアは総じて会食を危険視する報道ばかりで、家庭内での具体的な感染対策に言及していないのが気になる。もっと生活に近い内容の記事がほしい。経済崩壊も深刻だ。収入が減ってしまった場合、生活に困ってしまった場合、飲食店などを応援したい場合など、これからできること、必要になるかもしれないことに焦点を当ててほしい。(松浦美季 28歳 神奈川県)
■一覧できる図表に期待
一覧できる図表を期待していた。1月15日朝刊は、1面に都道府県別のステージ4に相当する指標の数を示す日本地図、2面に都道府県別の六つの指標と現状の一覧、17面に都道府県別新規感染者数の時系列グラフが掲載された。それぞれの訴求力を評価したい。願わくば、2面にあった六つの指標がそれぞれ時系列でどのように推移したのか。緊急事態宣言発出のタイミングが適切だったのかを評価できるような記事や図表をぜひ示して欲しい。(福岡泰 59歳 千葉県)
■要請と勧告、違い示して
1月16日朝刊の時時刻刻「病床 民間に確保迫る」を読んで、いまひとつピンとこなかったのが、感染症法改正における要請と勧告の違いだ。協力を求めることができる要請と罰則を伴う命令に等しい勧告。その違いをもっとわかりやすく説明してほしい。どのような場合に要請から勧告となるのか、その基準は何なのかを教えてほしい。勧告を発動して得られる効果は、表面上の病床確保以外に何があるのか。もっと掘り下げてほしい。(小野和博 57歳 福岡県)
<的確なデータ分析、原点を再確認>
「ウイルスが歴史の行方を決めることはない、それを決めるのは人間である」。イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏のこんな言葉を最近、知りました。
では、コロナ禍への対応を決める私たちは、目に見えないウイルスにいかに向き合い、どう行動すべきなのか――。その判断に欠かせない材料になるのが、客観的な「データ」です。データはときに都合よく切り取られたり、誇張されたりします。公的機関がデータを正確かつタイムリーに公表することはもちろんですが、報道機関がそれをどう分析し、客観的に伝えるか。モニターの皆様から厳しい目と期待が向けられていることを改めて肝に銘じました。
コロナ禍では、私たちの権利が法律で制限される場面もあります。恣意(しい)的な運用を許さないためにも、法律の趣旨や用語が何を意味し、普段の生活にどう影響するのかについて突き詰めることも必要です。
客観的立場から、わかりやすく、一つひとつのデータや言葉をあいまいにしない。この原点に立ち返り、コロナ禍での報道を続けます。(科学医療部長・西山公隆)
■紙面モニターになりませんか デジタル会員にご登録を
朝日新聞社は読者のみなさまの声を紙面づくりに生かすため、「紙面モニター」を募集します。
新聞記事に関するアンケートに、2週間に1回、パソコンからインターネットを通じてお答えいただきます。今回は第31期で、任期は4月から半年間。謝礼として回答1回につき1500円分の図書カードを任期終了時にまとめて進呈します。
▽応募方法 朝日新聞デジタルの紙面モニター応募用画面(http://t.asahi.com/shimen![]() )から=QRコード。多数の場合は選考します。
)から=QRコード。多数の場合は選考します。
応募にあたって、朝日新聞デジタルへの会員登録(有料会員または無料会員)をお願いします。朝日新聞デジタルのトップページ(https://www.asahi.com)から申し込みをしてください。家族の方が既に会員の場合でも、紙面モニターに応募するご本人が会員になってください。現在の第30期モニターの方は応募できません。
▽締め切り 3月1日(月)
◇東京本社発行の朝刊、夕刊の最終版をもとにしています。
*
公募で選んだ300人の読者の皆様に「紙面モニター」をお願いし、毎週、お寄せいただく意見の一部を紹介します。この欄は、編集局との「対話」の場を目指しています。紙面モニターの意見に対し、編集局の担当部署の責任者が答えます…