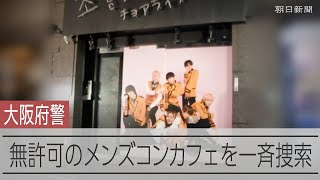(社説)緊急事態宣言 事業者支援が不十分だ
緊急事態宣言で新型コロナウイルスの感染急拡大を抑えるには、多くの国民の協力が欠かせない。ところが政府は4都県を対象に2度目の宣言を出しながら、セットで示すべき事業者への支援策は不十分なままだ。
要請通り時短営業する飲食とカラオケ店に支払う協力金の上限は、1店あたり日額4万円から6万円に増やす。ただ、従業員数や店の家賃によっては赤字が避けられない事業者もあるだろう。前年の収入の一定割合を支給するなど、事業規模に応じた支援が求められる。
宣言は、飲食店の納入業者の経営にも打撃を与える。在宅勤務が徹底されれば、オフィス街の弁当販売業者も顧客が急減しよう。パチンコ店や映画館などの遊興施設も、時短営業を呼びかけられている。
問題は、飲食・カラオケ以外のこうした店への財政支援が打ち出されていないことだ。
業種を問わずに収入が半減した中小企業を対象とする持続化給付金を、政府は1回目の宣言に合わせて設けたが、近く申請受け付けを締め切る予定だ。確かにこの給付金は不透明な事務委託が批判され、不正受給も多発している。だからといってコロナ禍の長期化で苦境にある事業者を、支援しない理由にはならない。持続化給付金をやめるのであれば、別の支援策を早急に決めるべきだ。
冬場に感染が急拡大する恐れがあることは、十分に想定できたはずだ。社説でも、感染の動向に応じて柔軟に対応できるよう、政策の準備を求めてきた。
ところが、昨年末に追加経済対策を決めた際は、脱炭素社会に向けた研究支援基金や雇用調整助成金の特例縮小といった経済の正常化をめぐる議論に終始し、有事への備えを怠った。
支援が後手に回った原因が、経済活動の再開を前のめりに進める政権の基本姿勢にあることを、菅首相は認識する必要がある。政府が今回改定した対処方針には「感染拡大防止を最優先」と明記された。言葉通り実行しなければならない。
いまは政策の重心を、コロナ後の社会づくりから、命や暮らしを守る対策に戻すべき時だ。感染収束が見通せないなか、「Go To」のような旅行や飲食の需要喚起策を再開することはありえない。今年度3次補正予算案に計上した1兆円超の財源は、事業者への直接助成などに振り向けるべきだ。
感染を抑止できなければ、1カ月間とする宣言期間の延長は避けられず、経済活動の制限強化も迫られよう。その時、どんな支援策を追加するのか、あらかじめ詰めておく必要がある。同じ失敗は繰り返せない。