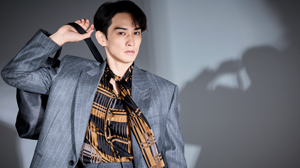生成AI登場で生じた技術と社会のギャップ 法ではないよりどころは
計り知れない価値を生み出す一方、社会に新たな問題や懸念をもたらしつつあるAI(人工知能)。倫理や法律の観点から科学技術と向き合い、課題解決をめざすELSI(エルシー)の役割について考える「ELSI大学サミット」が15、16の両日、東京都内で開かれた。大学や政府、メディアが果たす役割と、その連携の重要性について、研究者や経営者らが話し合った。
(中央大ELSIセンター、大阪大社会技術共創研究センター主催、朝日新聞社など後援)
【基調講演】須藤修・中央大ELSIセンター所長
1月、世界に衝撃を与えたのが中国企業ディープシークのAIだ。従来に比べて大量の「学習」をせずとも、人間の熟練者を上回るプログラミング能力を示した。大学で学ぶ政治学や科学の問題も、人間並みか、しのぐ回答ができる。
しかも問題を解きながら「待って待って……アハモーメント(ひらめいた!)」と、(それまでの自分の解法を)反省するようになった。そんなプログラムはしていないのに。開発者自身の想定を超え、AI研究者たちが恐れてきたことが起きつつある。
2月に発表された米オープンAIのGPT4.5も、これまでなかった直感的な回答ができるとされている。
ショッキングであり、世界中の経営者や研究者の頭の中にAGI(汎用(はんよう)人工知能)の概念も浮かび始めている。人間と並ぶ、あるいは超える能力を持つとはどういうことか。AGIの定義の議論も始まっている。
誰でもふつうの言葉でAIを扱えるようになった。今起きているAIの民主化によって、医療福祉、教育、金融、国防など、社会の重要なシステムがAIを軸に複合的に変動していく。
だからこそ、ELSIの観点からの取り組みが必要だ。経済、市民社会、行政、法曹、教育、就労者の代表らが、ひざを交えて討論できる環境が欠かせない。
法や政治的理念に加え、(AI開発の)エンジニアリング側もしっかりと提案していくべきだ。
私が議長を務める総務省の会議でまとめたAI事業者向けの指針も、昨年4月に初版を出し、近く新版を発表する。AIはものすごいスピードで進化する。政府の指針も、どんどんバージョンアップを繰り返す「リビングドキュメント」であることが欠かせない。
【基調講演】岸本充生・大阪大社会技術共創研究センター長
新しい科学技術が社会に実装される時、つまずくことがある。安全性、プライバシーや個人情報保護、不公平や悪用の恐れ。しばしば炎上も起きる。
一方で「何かあったら、どうする?」と怖がるだけでは、新しいことが何もできなくなる。
こうして科学技術と、社会の間に生まれるギャップをELSI(倫理的・法的・社会的課題)と呼んでいる。
ELSIという言葉は30年以上前、ヒトゲノムを解読するプロジェクトで既に研究の対象になっていた。
ゲノムがすべて解読された後に、社会にどんな悪影響が出るか、研究前から予測して備えよう――。このコンセプトは今でも先進的で、ドローンや自動運転など社会実装が見込まれる「エマージングテクノロジー(新興技術)」に広く適用できる。
ところが、生成AIはいきなり登場した。著作権の課題など、技術的にできることと法や社会との間に大きなギャップが生じてしまった。
技術革新の速度がどんどん増す中では、判例などに基づく法規制は、後追いにならざるをえない。SNSに見られるように、世論も不安定で、今までのようには法や社会に頼りづらくなっている。
そこで、相対的によって立つ視座として「倫理」が求められるようになってきた。企業は続々とAIの「倫理原則」や「倫理指針」を策定し、倫理の観点に基づいて意思決定をしようとしている。
大学でも、以前からある医学系以外にも、情報科学や人文社会科学を含めて研究倫理の審査が導入されつつある。
AIを使った製品やサービスを社会に実装する前には、倫理面で許容することができないようなリスクがないかを確認することが重要になるだろう。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら