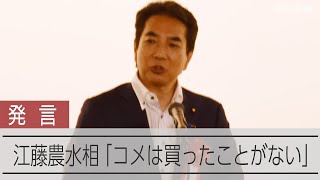第3回不安が強すぎて不登校 予防教育の専門家「学校という環境にも一因」
不登校の一因には、「不安症(不安障がい)」もあるといわれる。文部科学省の2023年度調査では、不登校の小・中学生の2割以上に「不安・抑うつの相談があった」という。子どもたちは学校生活の何に不安を感じているのか。不安の問題の予防教育に取り組む公認心理師の浦尾悠子さんに聞いた。
本人の特性と環境のミスマッチ
――不安がどのようにして不登校につながるのでしょうか。
不安は、身に迫る危険を避けるために必要な感情です。でも必要以上に強かったり、非常に長く続いたりすると日常生活に支障が出てしまう。そうした場合、不安症と診断されることがあります。
不安症というのは不安の病気の総称で、何に対して不安を感じるかは人によって様々ですが、不登校の子どもによくみられるのは対人不安です。友達にどう思われているか不安、先生に怒られるのが怖い、そもそも教室など集団の場にいるのが怖い、といった話をよく聞きます。
――不安症というと、人前に出るのが怖いとか満員電車が怖いといったイメージです。
ある時みんなの前で恥をかいてしまい、それ以来人前に出るのが怖くなったなど、不安の原因や対象がはっきりしている場合もありますが、不登校の子どもの場合、本人の気質や特性、発達段階、人間関係、生活環境など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが多いです。
学校は「同調圧力の高い空間」
たとえば対人関係の悩みにつ…