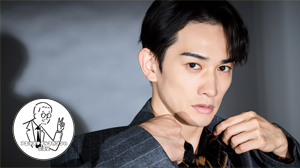自治体職員も戸惑う制度情報の分散 「1カ所にまとまっていたら…」
Re:Ron連載「知らないのは罪ですかー申請主義の壁ー」第6回
「どこか1カ所に全ての社会保障制度の情報がまとまっていたらいいのに。なぜそういったものがないのだろう」
そう感じたのは、大学卒業後に病院で社会福祉士として働きはじめた1年目のことでした。
病院の社会福祉士は、患者や家族の病気やけがによって生じる困りごとの解決をお手伝いすることが主たる業務で、社会保障制度の情報提供やその活用をサポートすることが多い仕事です。
社会保障制度はさまざまな実施主体によって提供されています。当時、患者さんの居住する自治体、都道府県をはじめ、健康保険組合、年金機構、労働基準監督署、ハローワーク、厚生労働省、いろいろな組織のホームページを行き来しては、利用できる制度を探し、内容を確認する日々を過ごす中で、感じた疑問でした。
あれから15年以上が経ちましたが、いまだに現状は変わっていません。
検索エンジンのGoogleやYahoo!のように、探すときはまずはこのサイトという媒体が社会保障制度においては存在していないのです。自治体によっては、一部の社会保障制度の情報をホームページに掲載していない場合もあります。私たちの権利であるにもかかわらず、です。
コロナ禍に入り、少しだけ変化が見られました。厚労省が「生活を支えるための支援のご案内」という、40弱の制度を掲載したリーフレットを作成し、ホームページから閲覧、ダウンロードできるようにしたのです。経済支援制度が主でしたが、この仕事についてはじめて、一定程度の網羅性のある制度一覧を出されたことに驚いたことを覚えています(ですが、お金に関する制度は100程度ありますので、40でも少ないのです)。
ですが、このリーフレットは、その後2023年5月31日をもってホームページでの掲載は終了になりました。情報の一部は、厚労省のホームページ内の「新型コロナウイルス感染症に関するくらしや仕事の情報をまとめたページ」に引き継がれましたが、掲載される制度の数は少なくなってしまいました。
被災者の生活に関しては、内閣府が防災情報のページに被災された方への支援制度をPDFでまとめています。元日に起きた能登半島地震で被災された方で今まさに情報を必要とされている方がおられると思います。インターネットの環境がなく、またデジタルの活用が難しい方など、この情報にたどり着けない方もいるかもしれません。ぜひ、お近くの方、お知り合いの方で必要としている方にお知らせいただけたらと思います。
これまでの連載では、社会保障制度の申請プロセスでの障壁などを指摘しました。
社会保障制度が申請主義をとることは、私たちの申請する権利を認めるもので、それ自体が“悪”ではありません。ですが、利用に至るまでの障壁が存在している以上、社会保障制度をセーフティーネットとして機能させるためには「申請する権利の行使をサポートする施策」が社会の隅々に張り巡らされていることが必要であると考えます。
では、公助である社会保障制度のアクセスが自助頼みであるという矛盾は、どのように解消していくことができるでしょうか。
今後の連載では、申請する権利の行使をサポートするための施策や取り組みについて考えるための論点を具体例とともに示していきたいと思います。後半では海外の事例も取り上げたいと考えています。
管轄ごとに情報が分散
今回はまず、「情報の入手」について焦点を当てます。以下、これまで私がサポートしてきた方々を思い浮かべながら設定した架空の事例の男性を通して、情報入手のプロセスを見ていきたいと思います。この男性はどのような制度を利用できる可能性があるでしょうか。
39歳の会社員の男性。2カ…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら