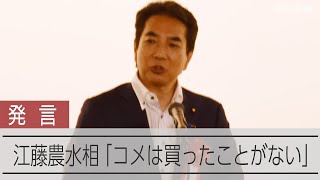植田総裁は本当に「仕事人」なのか 微修正に留まった金融政策正常化
この世界的で歴史的なインフレ下でも主要国中央銀行で唯一、お金のばらまきを続けているのが日本銀行だ。だが、さすがに超金融緩和の単純な継続というわけにもいかなくなったのだろう。日銀は28日、政策の柱であるイールドカーブ・コントロール(YCC、長短金利操作)の一部修正に追い込まれた。
植田和男総裁になってから3回目の金融政策決定会合(年8回開催、メンバーは総裁以下9人)で初めての政策変更となる。
黒田東彦前総裁の時代の10年間、日銀はアベノミクスの主柱となる「異次元緩和」をずっと続けた。結果として政府債務の膨張と日銀の財務悪化が進み、その影響とみられる円安がエネルギー資源価格の高騰に端を発した国内インフレに拍車をかけている。
金融政策を知り尽くしている学者出身の植田氏が今春、総裁に就いた意味は、当然、この異次元緩和から抜け出し、金融政策を一刻も早く正常な状態に戻すことにあるはずだ。
金融市場はそういう理解で植田日銀の緒戦に注目してきた。だが4月、6月の決定会合でも植田日銀は動かず、金融市場は肩すかしを食った。3回目となる今回の決定会合でようやく一部修正に踏み切ったものの、内容的にはまったくの微修正である。
日銀ウォッチャーたちが注目していたのは、YCCの廃止に植田日銀がどう乗り出すかだった。日本国債が投機的なファンドなどから売り浴びせられたり、本来の長期金利の水準がゆがめられていたりといった問題点が多いのは、この政策が原因となっているからだ。
この点で植田総裁の真意はどこにあるか。読み解くカギは、まだ総裁人事が動き出す前の昨年7月、植田氏が日本経済新聞「経済教室」に寄稿した論考「日本、拙速な引き締め避けよ 物価上昇局面の金融政策」のなかにある。植田総裁の理論家としての本音がそこににじみ出ているからだ。植田氏はこう書いていた。
「今後、持続的な2%インフ…