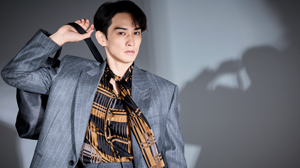国のコロナ対策に「怒り買うだけ」 病院会会長の思い
新型コロナウイルスの感染者数は右肩上がりに増加を続け、病床使用率は高止まりが続く。感染が確認された人で重症者は1014人(20日時点)と過去最多となるなど、医療の逼迫(ひっぱく)度も高まってきている。長野・相沢病院理事長で、約2500の病院が加盟する日本病院会の相沢孝夫会長(73)は「国は宣言だけでなく、人々にさらなる危機意識を持ってもらうための強いメッセージと、病院間の役割分担などを促し、地域でコロナを受け入れるための青写真を描くべきだ」と話す。感染拡大が続く現状と今後の展望について聞いた。
――国内で新型コロナウイルスへの感染が確認された人は累計で30万人を超えました。感染が拡大する現状をどう見ていますか。
「国は特別措置法に基づく緊急事態の宣言を11都府県に発出しました。ですが、おそらく今のやり方では感染拡大は止まらないと思います。非常に憂慮すべき状態です。人々の行動に制限をかけることは大事ですが、『これは危ない』『大変な状況が今起こっているんだ』と危機意識を高めることの方が重要です。健康で丈夫なひとに健康診断を受けてと言っても受けません。それと同じです」
緩さ漂う緊急事態宣言
――危機意識を高めるためにはどうすれば。
「もっと強い宣言、メッセージが必要です。昨年緊急事態が発出された時とは感染者数も医療提供体制の逼迫(ひっぱく)度も違います。なのに普通の空気が流れている気がしませんか。人と人の接触機会を減らし、移動も少なくすれば広がりが抑えられることはすでに分かっています。でも今回の宣言にはどこか緩さを感じます。医療提供体制についても国がリーダーシップを発揮して、病院間の役割分担や連携を促すなど、早急にみんなで協力し合う体制を作るべきだと思います」
――その医療提供体制、特に病床の逼迫度は深刻です。日本は「ベッド大国」と言われ、人口千人あたりのベッド数は「13」と米国(2.9)や英国(2.5)と比べ突出して多いというデータがあります。なぜ逼迫するのでしょう。
「国内の医療機関には『一般病床』『療養病床』『感染症病床』などに分けられ、計約160万の病床があります。ですが、コロナ患者を受け入れられる病床は限られています。さらに医師や看護師の数も米国などの先進国に比べれば決して多くありません。入院者の絞り込みもあまりなされてこず、高齢者や基礎疾患がある患者は軽症や無症状でも入院させていた。そうなればベッドはたくさん必要になってきます」
「厚労省は病床確保策として感染症法の改正を打ち出し、民間病院への対応を迫ってきました。でも各病院にはその地域での役割、使命があります。元々持つ機能が違えば、配置されている医療従事者の人数も違っていて、やれる医療には限界がある。だから、負担を押しつけ合うのではなく役割分担をするべきです。『あなたの病院はこういう機能ですから、この緊急事態にはここを担ってください』とか、『通常医療はほかの病院に割り振りますから、コロナの重症者をみてください』などと、まずは地域でコロナを受け入れるための青写真を描くべきです。国がそれを描き都道府県が調整する。そうすればもっと早く医療提供体制が整うはずです」
――理事長を務める長野・相沢病院では、コロナ患者を受け入れています。
「この病院は救命救急センターとして、救急患者の受け入れを断らないことを使命としています。急性期医療を担う病院としての役割もあります。ただ、コロナ患者も受け入れるとなるとコロナ以外の医療において、延期や中止をせざるを得ない部分が出てきます。病床をあけないことにはコロナ病床も確保できませんし、重症者を受け入れるには看護師も相当数が必要です」
コロナ患者受け入れの難しさ
――通常の医療を犠牲にすることによる経営面への不安もあります。
「そういうことは僕は関係な…
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら