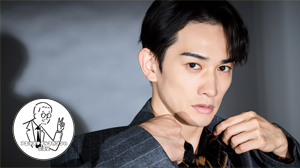(社説)インドネシア 民主化 後退させぬ道を
四半世紀にわたり積み重ねてきた民主化の実績を損ねてはならない。それこそが世界4位、2億7千万の人口を抱える東南アジアの大国が、国際社会の要として重責を果たす原動力だからだ。
5年に1度のインドネシア大統領選が投開票され、国防相のプラボウォ氏(72)が勝利を宣言した。10月に就任し、国民の平均年齢が30歳以下の活気あふれる新興国のかじ取りを担う。
2億人を超す有権者が国家元首を直接選ぶ「世界最大の直接選挙」だ。3候補の争いに大きな混乱はなく、民主主義の成熟ぶりを印象づけた。
ただ、懸念もある。
プラボウォ氏は、1998年まで約30年間、独裁を続けたスハルト元大統領の元娘婿だ。国軍幹部として、民主化運動の弾圧など人権侵害に関わった疑いで軍籍を剥奪(はくだつ)された過去がある。
勝利を確実にしたのは、SNSなどを使ったイメージ戦略で独裁の記憶が薄い若者への浸透に成功したからだ。過去を知る世代には不信感も根強い。大統領に就任したあかつきには、すべての国民の不安を払拭(ふっしょく)する責任がある。
ジョコ大統領の「後継」の立場を得たことも追い風になった。ジョコ氏は同国初の庶民出身の大統領として2期約10年を務める。経済成長やインフラ整備などで実績も重ね、今でも70%前後の高い支持率を維持している。
だが2期目では強権的な手法も目についた。独立機関「汚職撲滅委員会」の権限を弱め、大統領や政府への侮辱を犯罪とする刑法改正を行うなど言論統制を強めた。
大統領選でプラボウォ氏は、ジョコ氏の長男ギブラン氏(36)を副大統領候補に指名した。規定の年齢に達していなかったが、憲法裁判所はギブラン氏が地方首長を経験していることを理由に、出馬を認める判断をした。
その憲法裁の長官がジョコ氏の義弟だった。一族が政治的な影響力を残す思惑で民主的ルールをゆがめたのでは、と批判されたのは当然だ。
インドネシアには、退潮が指摘される東南アジアの民主主義の「防波堤役」が期待されているだけではない。
米欧と中ロの対立が深まる昨今、国際社会の分断の「橋渡し役」としての存在感も増す。単に人口規模や経済力だけでない。民主化を進め、法の支配や人権など普遍的価値を重視してきた努力のたまものと自覚すべきだ。
その歩みを止め、国際的な信頼を失えば、安定や発展は見込めないことを、プラボウォ氏は忘れてはならない。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら