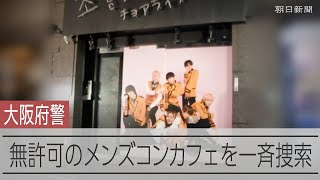(社説)大雪への備え 「命を守る」を最優先に
年末から年始にかけて、日本列島は強い冬型の気圧配置となり、広い範囲で大雪の恐れがある。路面の凍結や車のスリップ事故、屋根からの落雪、停電などへの警戒が必要だ。
今年は新型コロナの影響で帰省や遠出を控える人が多いだろうが、たとえ近場であっても、柔軟に日程を変更するなど、慎重な行動を心がけたい。
特に注意すべきは車の運転だ。今月中旬の大雪では、新潟県の関越自動車道で最大約2100台の車が立ち往生した。
車内に長時間閉じ込められると、一酸化炭素中毒やガソリン切れで凍死する危険もある。降雪の多い地域へ行く前には、チェーンはもちろん、除雪のためのスコップ、毛布などの備えを怠らないようにしよう。
先の関越道では、道路管理者のNEXCO東日本に多くの判断ミスがあった。渋滞が始まってから通行止めにするまでに半日以上かかり、事態を悪化させた。約1千台あった滞留台数を当初約70台と発表し、混乱に拍車をかけた。こうした誤りは大災害につながりかねない。
同社は早い段階での人員投入や巡回強化などの対策をまとめた。他社もこれを参考に態勢の見直しを進め、同様の混乱を招かぬよう徹底してほしい。
大雪による立ち往生は、2年前に福井県の国道8号で約1500台が滞留したのをはじめ、過去にも何度か起きている。大切なのは、交通の動脈を何としても確保しなければという考えにとらわれ過ぎないことだ。
台風で猛烈な雨や強風が予想される場合、事前に通行止めとする例があるように、大雪でも基準を設けておくことを検討してよいのではないか。雪と雨とで予報の精度が違うという課題はあるし、物流の維持はむろん重要だが、人命が失われてしまっては元も子もない。
一般道路の管理者も、影響が出そうな地域を把握して早め早めに情報を出すべきだ。
車の運転以外でも気をつけねばならないことは多い。
消防白書によると、雪関連の死者は昨年までの10年で850人。最も多いのが雪おろし時の転落事故だ。複数で作業し、ヘルメットや命綱をつけ、埋もれた時のために携帯電話を持つ。こうした準備が欠かせない。
14年の大雪では首都圏が2週連続で機能マヒし、山梨県などの山間部で集落が孤立した。過疎化と高齢化が同時に進む地域が少なくない。外部とのつながりが断たれた場合の対策を、自治体も確実に講じておきたい。
日本海側などでは吹雪になれば平地でも見通しは悪くなる。最新の予報に注意し、くれぐれも無理をしないことが肝要だ。