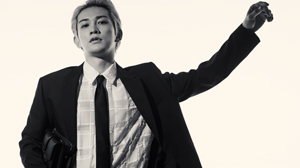(社説)増える自殺者 救える命、支援重ねて
新型コロナ禍が人々の生活に重大な打撃を与えている表れと見るべきだろう。7月以降、自殺者の数が大幅に増えている。
かねて懸念されていた事態だ。政府・自治体は実情の把握に努め、考えられる対策を早急に講じる必要がある。
警察庁によると、7~9月の自殺者は毎月1800人を超えた。男性が依然多いが、女性は各年代で増加傾向にあり、8月には前年同月比で4割も多い651人が自ら命を絶った。
厚生労働相の指定を受け調査研究にあたる「いのち支える自殺対策推進センター」は先月、緊急報告を出した。「無職の女性」「同居人がいる女性」が全体の自殺死亡率を押し上げているのが特徴だという。
女性が多いパートやアルバイト、派遣で働く人たちが仕事を失う。一斉休校や在宅勤務の広がりでストレスが高まり、家庭内暴力が増える――。言われていたことがコロナ禍の長期化によって深刻さを増し、その悩みや苦しみが最も悪い形で顕在化しているといえそうだ。
実際、非正規で雇用される女性は4月以降、前年同月よりも平均で約70万人減っている。一方、家庭内暴力の相談件数は前年比で5割前後の増加という。
若年層も気がかりだ。8月は高校生42人、中学生16人が亡くなった。窓口には「オンライン授業についていけない」「休校明けにクラス替えがあり、周囲になじめない」といった相談が相次ぐ。人気俳優の訃報(ふほう)後、若い世代を中心に「後追い」の傾向もみられるという。
自殺者の数はかつて年間3万人を超えていたが、近年の対策が功を奏して2万人近くにまで減った。しかしこのままでは逆戻りしかねない。
何より大事なのは生計の安定だ。先の報告は、春以降の政府の緊急小口資金や住居確保給付金が自殺を抑止した可能性があると評価する。だが年内で支援が途切れる人もいる。延長を検討すべきではないか。
電話やSNSを利用する相談態勢の充実も急務だ。
悩んでいる人は増えているのに、「密」を防ぐため、相談に乗るスタッフの数や稼働時間を絞らざるを得ない現実がある。拠点となる事務所の環境整備や相談員を増やすための研修の強化など、やれることはいくつもある。国・自治体は必要な費用を惜しんではならない。
メディアも、自殺の連鎖を絶つために世界保健機関が定めた指針を踏まえながら、日々の報道にあたる責任を負う。
SOSの声を上げやすくし、心身の負担を軽くするための仕組みを張り巡らせることで、一人でも多くの命を救いたい。