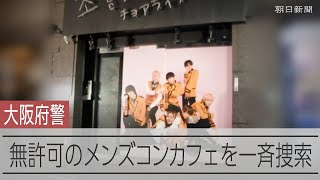噴霧で「空間除菌」推奨せず ウイルス除去の効果「不十分」 厚労省=訂正・おわびあり
新型コロナウイルスの感染対策として、消毒液を噴霧して「空間除菌」を図ろうとする動きがある。だが物品消毒での効果が確かめられた界面活性剤を含め、噴霧によって空間内のウイルスを取り除く方法は確立されていない。厚生労働省も「噴霧は推奨しない」との立場だ。物質や濃度によっては有害となる恐れもあるという。
山梨県身延町は5月、公共施設のほか小中学校の各教室に2台ずつ、「次亜塩素酸水」の噴霧器を設置。食品加工や医療現場で使われてきた消毒液で、消毒用アルコールの品薄もあり注目されるようになった。
しかし3日目に使用を中止。安全を確認するという。西日本の交通事業者も車内で次亜塩素酸水を噴霧していたが中止を決めた。
経済産業省などによると食塩水などを電気分解して作られる次亜塩素酸水は、装置から溶液を物品などにかけ流して使うのが一般的。分解しやすく、時間とともに効果が薄れる性質があるためだ。新型コロナへの効果は独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE)が調査中の段階だ。
NITEなどは家庭用洗剤に含まれる「界面活性剤」が新型コロナに有効と発表したが、布などに染みこませて拭く物品消毒を想定した評価だ。これらを噴霧に使えるかについて、厚労省結核感染症課は、新型コロナに限らずウイルス全般に対して「空間の除染には不十分なため、推奨しない」としている。ウイルスが空気中にいても、噴霧された有効成分と出合う可能性は極めて低いと考えられるという。
次亜塩素酸水など、電気分解で生成した水の研究者らでつくる一般財団法人、機能水研究振興財団の堀田国元理事長によると、本来の用途として噴霧は想定されておらず「有人空間での噴霧の有効性や安全性を確かめた研究はない」という。また「次亜塩素酸ナトリウム」という物質と塩酸などを混ぜて作るタイプは「濃度などの規格がなく、噴霧は危険」と話す。厚労省も「吸引すると有害」としている。
大久保憲・東京医療保健大学名誉教授(感染制御学)は「そもそも新型コロナの感染経路は飛沫(ひまつ)感染や接触感染が中心で空気感染対策をする意味は大きくない。換気をする方が効果的」と話している。(小林未来)
<訂正して、おわびします>
▼4日付社会面の新型コロナウイルスの消毒液噴霧の有効性に関する記事と、12日付「新型コロナ」面「有効な消毒液と使い方は?」の記事で、いずれも機能水研究振興財団の説明として「次亜塩素酸水の生成装置メーカーなどでつくる」とあるのは「次亜塩素酸水など、電気分解で生成した水の研究者らでつくる」の誤りでした。メーカーは財団の運営主体ではなく、賛助会員でした。