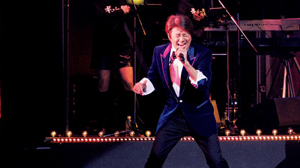納骨堂の経営許可は妥当 「環境悪化」住民起こした裁判、地裁が棄却
屋内で遺骨を供養するビル型納骨堂の周辺住民6人が、大阪市に経営許可を取り消すよう求めた訴訟の差し戻し審の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は25日、住民側の請求を棄却した。「生活環境が著しく損なわれる具体的な恐れは認められない」として、市の許可を適法と判断した。
原告は同市淀川区の納骨堂(6階建て)の100メートル以内に住む住民。訴訟は2017年に起こされ、地裁は当初、そもそも住民に裁判で訴える「原告適格」がないと訴えを却下。大阪高裁と最高裁が「適格がある」と判断し、ようやく市の許可の是非が判断された。
判決は、納骨堂の外観がビルと変わらない上、住民から挙がっていた反対意見はお経の音や線香のにおいなど「抽象的な懸念と主観的な嫌悪感」を述べるものだと指摘。市が審査基準としていた、公衆衛生上の「生活環境の著しい悪化」とは直接関係がないと判断した。
さらに、設置主体の宗教法人が市に提出した書類からは原告側が言うような経営破綻(はたん)の可能性は読み取れず、檀家(だんか)や信徒の設置要望もあったと言及。審査は合理的で許可に「裁量権の逸脱はない」と結論づけた。
判決後、会見を開いた原告の能勢治郎さんは「不当な判決だ。いつか遺骨が放置されるのではと不安に思いながら生活している」と話した。弁護団によると控訴する方針という。