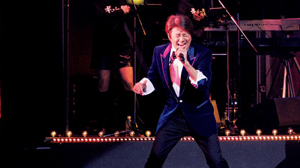富士山が大噴火なら…灰はドーム400杯分、必要備蓄「1週間以上」
富士山の大噴火に備え、内閣府の有識者検討会は21日、灰の積もる量などに応じて地域の危険度を4段階に分け、避難の必要性を示す初の指針案をまとめた。降灰の影響で首都圏でも停電や交通、通信の乱れなど、都市機能のまひが想定され、「自宅で生活を続ける」を基本としつつ、降灰量が30センチ以上になれば命の危険があり、原則避難を求める。
富士山は過去5600年に約180回の噴火があった活火山だが、江戸にも火山灰をもたらした宝永噴火(1707年)を最後に約300年間、噴火が確認されていない。
相模原に30cm、新宿に3cmの灰
政府の中央防災会議は2020年、同程度の大噴火が起きた場合、東京都新宿区付近で3センチ以上、相模原市付近で30センチ以上など福島から静岡まで11都県に降灰があるとする予測を公表。富士山から離れた地域でも大規模な鉄道の運行停止や、停電や通信障害、上下水道の使用制限なども想定され、今回は住民の対応策などを初めて示した。有珠山(北海道)や浅間山(群馬・長野県)、阿蘇山(熊本県)など全国の活火山への応用も想定する。
危険度4段階で避難判断へ
指針案は降灰量や物資の輸送に使う道路の状況によって、地域をステージ1~4に分けた。最も危険なステージ4(30センチ以上)は原則避難で、降雨時は木造家屋の倒壊の可能性もある。降灰量が30センチ未満では「できる限り自宅等で生活を継続することが基本」としつつも、ステージ3(3センチ以上30センチ未満)は道路の除灰が追いつかず物流に影響が生じ、生活物資の入手が困難な状況も想定される。
そのため、指針案は平時からの備蓄の重要性を呼び掛け、噴火の兆候などがあれば、事業者には従業員の出勤抑制やテレワーク体制の確認などを求める。
検討会の座長の藤井敏嗣・東大名誉教授は「発生頻度が少ない火山灰に対しては、自治体や企業、国民の間で、準備が行き届いていない」と述べ、事前の理解と備えの必要性を訴えた。
大量の灰への対策 企業や自治体は
富士山が大噴火すれば、首都圏を含めて広範囲で降灰が予想される。健康への影響や都市機能のまひ、東京ドーム約400杯分の灰の除去も想定される中、どのような備えができるのか。
富士山が噴火したときの火山灰は、どんなもので、街の何に影響があるのか。記事後半では、火山学者の見方やインフラ企業、自治体の対策をお伝えします。
火山灰は直径2ミリ以下と細…
- 【視点】
来るべき富士山噴火にあっては、まず私たちは歴史を参照すべきであろう。直近の富士山噴火は、記事中にある通り1707年の宝永噴火である。 宝永噴火によって風下にあった小田原を本拠とする小田原藩は激甚な被害を受けた。小田原は戦国時代における
…続きを読む