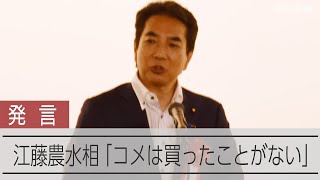戦争回避の目的もあった国債抑制 崩れた不文律、防衛費調達で発行
戦争とデモクラシー⑥ 「禁じ手」を破った先は
一度緩めた財政規律を取り戻すことは難しい。
戦前、高橋是清蔵相は、景気回復が実現すると財政引き締めに転じようとした。積極財政の打ち切りは、二・二六事件で高橋蔵相が暗殺されて頓挫したとされる。だが、大蔵省の「昭和財政史」によると、実際には積極財政からの転換は事件前から「絶望的であった」という。
安倍晋三元首相以降の政権は、デフレ脱却のために財政出動を続けてきた。コロナ後は物価上昇が目標の2%を超えたが、財政出動を求める与野党の合唱はやまない。今年度補正予算の規模も前年度を上回る13.9兆円に膨れあがった。
いまの積極財政の中身は、主に国民への現金給付や半導体への補助金などで、軍事予算が中心だった戦前とは違う。自衛官が暴走し、政治を支配しているわけでもない。ただ、財政規律が崩壊するなかで、たがが外れて防衛予算が膨張する恐れがある。
実際、その兆しはすでにある。
岸田文雄前首相は2022年末、戦後の抑制的な安全保障政策を転換し、防衛費予算を大幅に増額し、27年度に国内総生産(GDP)比2%にすることを決めた。その際、歴代政権の「禁じ手」を破り、防衛費の調達を目的とした国債の発行を認めた。
1947年に施行された財政法は、将来への投資目的以外の国債発行を禁じている。その理由について、制定に関わった大蔵省の平井平治は、施行直後に出版された「財政法逐条解説」にこう記した。
「公債のないところに戦争はないと断言し得る。本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書保証するものであるともいい得る」
100年をたどる旅―未来のための近現代史
世界と日本の100年を振り返り、私たちの未来を考えるシリーズ「100年をたどる旅―未来のための近現代史」。今回の「デモクラシーと戦争」編第6回では、前回(第5回)に続き、財務当局が世論の強い批判にさらされた戦前と現代の共通項を探りながら、「財政」とデモクラシーの関係を考えます。
高橋是清蔵相らに「戦争の回避」の意図
この発想は戦前にさかのぼる。高橋蔵相以下の大蔵官僚が積極財政を打ち切ろうとしたのは、単に財政の健全性を維持するためだけではなかったのだという。
蔵相や大蔵省幹部として戦時財政を担った賀屋興宣(かやおきのり)は戦後、「更に大きな国家の全局からの基礎的考え方があったのである。それは、戦争の回避・平和の維持である」と振り返っている。
高橋蔵相は、日本が軍事予算を増やせば、米国とソ連を巻き込んだ軍拡競争になり、国防力がかえって低下すると考えていたと賀屋は言う。
一方で、いまの財務官僚には…