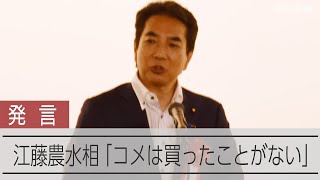幻の「不知火」36年ぶりに撮影 熊本の高校生ら、地元漁協が協力
蜃気楼(しんきろう)の一種で、熊本県の八代海だけに出現するといわれる「不知火(しらぬい)」。研究を続けている熊本県立宇土(うと)高校科学部地学班の生徒たちが3日未明、不知火とみられる現象を観測し、撮影した。地元漁協の協力を得て再現を試みた。
いさり火などの光源が横に連なって見える不知火の出現は、公的に残る記録としては1988年9月に熊本県不知火(しらぬひ)町(現・宇城(うき)市)で撮影され、現在は宇城市教育委員会が管理している写真に収められた画像が最後とされる。
宇土高校の科学部地学班は、古くから不知火の観望地として知られる宇城市不知火町の永尾(えいのお)剱(つるぎ)神社を観測地点に選び、南西方向に4~10キロ離れた川の河口3カ所に八代漁協から漁船を計3隻出してもらった。漁船には500ワットのLEDライトが積み込まれ、その光る様子を600ミリの望遠レンズで3日午前0時から3時間撮影した。
このうち神社から8.5キロ…
- 【視点】
不知火は、秋の季語だ。八代海の沿岸に現れる無数の火。人々が諸説あるその不思議な火の存在を受け入れ、見守り、季語として詠み継ごうとしてきたことも、人々が不知火の真実を追い求めてきたことも、その背景にあるのは自然への崇敬の念なのだと。そんなこと
…続きを読む