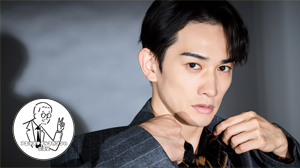実は貧困層と紙一重 雨宮処凛さんが見た「中間層」のもろさ
不安定な生き方を強いられた貧困層を取材し、自ら支援活動も続けてきた作家の雨宮処凛さんが、病気や介護など「中間層」にも役立つノウハウを集めた本を出版した。一貫して社会の底辺に目を向けてきた作家に、どんな心境の変化があったのか。
コロナ禍で出会った中間層 意外だった余力のなさ
――最新刊「死なないノウハウ 独り身の『金欠』から『散骨』まで」(光文社新書)。老人ホームの選び方まで盛り込まれて、困窮していない中間層にも役立ちそうです。執筆のきっかけは?
2020年から新型コロナウイルスの感染拡大にともなって生活が困窮した人を対象に、相談や支援を続けてきました。
そこで、つい最近まで中間層だったという人に数多く出会いました。
正社員として働き続けてきた人もいれば、フリーランスのインストラクターやエステティシャン、会社経営者も。かつては年収500万円以上あって、住宅ローンを組んで持ち家がある人が多くいました。
ところが、コロナであっという間にローンを払えなくなって貯金も底をつき、「まさか自分がこうなるなんて」とぼうぜんとしていました。
日本の中間層ってもっと余力があると思っていた。はたんのスピードの速さに驚きました。
家族持ちもいましたが、単身者がかなりいました。日本の様々な制度は両親プラス子ども2人みたいな標準世帯を想定しています。今や単身世帯が全体の4割近くを占めており、実態に合わなくなっているのをあらためて感じました。
「生活保護基準のわずか上」を支える制度が…
――それまで支援してきた貧困層との違いは何ですか。
非正規の仕事を転々として派遣切りや失業で住まいを追い出されるといったケースなど、コロナ禍前に相談を受けていたのはとても家なんか買えない人ばかりでした。
住宅関係の相談といえば「家賃が払えない」「賃貸を追い出された」。だから住宅ローンが組める時点で安定層と思っていました。でも実は、貧困との距離は近かったのです。
貧困層は自分の身を守るためにサバイバルの知識にたけていきます。相談先や使える制度、炊き出し情報などにすごく詳しい人も多いんです。
むしろ中間層の方がそういった知識がなくて丸裸で投げ出される分、衝撃が大きいですね。
支援のあり方も難しいです。
収入が生活保護基準をわずかに上回る人たちを支える制度がほぼありません。住宅ローンや家賃、子どもの教育費の負担に苦しんでいても制度が使えず、節約するしかないというもどかしさがありました。
今も東京では炊き出しにかつての何倍も長い列ができています。ホームレス状態の人だけではなく、制度のはざまにおかれた元中間層も並んでいます。
中間層だったけれど収入も貯金も失った場合、現実に使える制度が生活保護しかないケースが多いです。ところが、生活保護を勧めると強い抵抗を示される傾向がありました。
――生きるために必要な制度なのに、なぜでしょうか。
「自分は生活保護を受けるほ…
【春トク】締め切り迫る!記事が読み放題!スタンダードコース2カ月間月額100円!詳しくはこちら