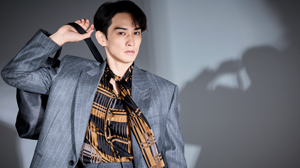16年間だけ走った「幻の鉄道」 生まれる前の記録を今に伝える大著
岡山市中区の旭川沿いで、内田武宏さんは大正から昭和の始めにかけて運行していた「三蟠(さんばん)軽便鉄道」の調査研究を続けている。わずか16年間、わが町を走っていた。自身が生まれる前の「幻の鉄道」の実相を定年後に追い求め、この秋、詳細な記録集を発刊した。
三蟠軽便鉄道は1915年、地元の有志らにより開業。岡山の海の玄関口として栄えた三蟠港と、岡山電気軌道の路面電車が走る牛窓往来(県道岡山牛窓線)が通る門田屋敷本町までの約7キロを結んだ。
時速約20キロの蒸気機関車が石炭や海産物といった物流を担い、旅客も運んだ。港の衰退や自動車の普及、道路整備などの都市計画にのみ込まれ、1931年に廃業した。
自身は42年生まれ。物心ついたころ、地域にはすでに鉄道の名残はなかった。唯一の接点は祖父の田畑で拾って遊んだ丸い石。払い下げの線路跡地を耕しており、枕木の下に敷かれていた旭川の河川敷の石だと聞かされた。
「どんな機関車が……」。そんな思いを抱き続けてきた。1997年の定年を機に調査研究を始めた。
地元の公民館での勉強会で地域史を学び続けた。かつての線路跡を歩いては面影探しに努めた。2012年には有志と研究会を立ち上げ、会長に就いた。
運営会社役員の子孫宅を探し当てた。蔵に株券や鉄道用地の測量図などが残っており、大量の資料を譲り受けた。乗車経験のある古老たちにも出会えた。
沿線の工場で働く「女工さん」がたくさん乗っていた。四国に渡るお遍路さんも多かった。犬養毅や竹久夢二も利用したかも……。多くの証言を得た。
「風光明媚(めいび)な旭川の風景を車窓から楽しんだに違いない」。ふるさとの歴史の一コマに触れるたび、言いしれぬ喜びを感じる。
着工から開通まで8カ月ほど。先人たちが大事業を短期間でやり遂げた結束力と行動力を現代に伝えたい。「記憶ではなく、記録としてしっかりと」
無数の資料や支援者との出会いに後押しされ、記録集の出版に着手。クラウドファンディングで費用は確保できた。B5判365ページ、税込み3300円の大著を研究会で仕上げた。
出版後もなお資料や情報は寄せられ、興味が尽きることはない。「三蟠軽便鉄道は地域の文化遺産。若い世代に伝えることが自分の務めだと自覚している」
SLが我がまちを走っていた歴史を知ることを、地域への誇りと自信につなげたい。SLに興味がない人にも伝えたい。たゆまぬ学びの興奮を。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら