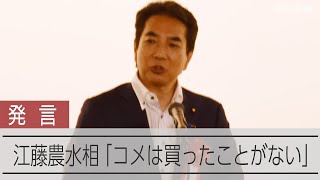変わらぬ日本の中絶 薬も術式も 劇作家・石原燃さんの気づき
鎖国していたわけでもないのに30年間、変わらなかった――。劇作家の石原燃さんは3月に東京・渋谷で上演する「彼女たちの断片」で「日本の中絶」をテーマに据えた。昨年12月、経口中絶薬の承認申請が厚生労働省に初めて出された。フランスや中国での承認から遅れること33年。劇では、登場人物の一人がこの中絶薬を服用したことをきっかけに、3世代7人の女性が性や中絶体験と向き合う。なぜ、日本の中絶は世界標準から外れていったのか。石原さんと考えた。
鎖国していたわけでもないのに……
――なぜ、「中絶」を書こうと思ったのですか?
中絶を研究している金沢大学非常勤講師の塚原久美さんの記事を2年前に読み、中絶薬がいまだに承認されず、英米では使われなくなった古い術式が残っているなど、日本の中絶医療が先進国の中で遅れていると知りました。
中絶は、日本の近代文学にもたくさん出てくる。「女の不幸」というある種の紋切り型の描かれ方です。それが、「医療の遅れ」と聞いてイメージが変わった。「不幸というより、女の権利の問題として怒っていいのでは?」と気づいた。医療を絡めると新しい切り口になり、中絶を受ける側の印象が変わってくると思ったのです。
――劇の冒頭、20歳の女性が避妊に失敗し、友人に相談。検索サイトで、中絶薬を処方してくれる海外の団体に行き着きます。
「ウィミン・オン・ウェブ」…