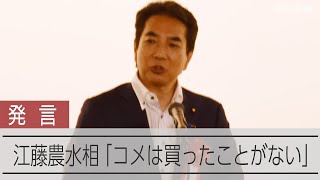生活保護基準額の引き下げは憲法違反? 神戸地裁判決の注目点は
国が2013年から段階的に生活保護基準を引き下げたのは憲法違反だとして、兵庫県内の受給者ら24人が引き下げの取り消しを求めた訴訟の判決が16日午後2時、神戸地裁で言い渡される。引き下げの経緯や神戸地裁判決の注目点をQ&A形式で整理した。
Q どれくらい引き下げられたの?
A 生活保護制度は「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を保障した憲法25条の理念に基づいている。国は13年8月から3回に分けて、生活保護費のうち、衣食や光熱費など日常生活に必要な費用にあたる「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げた。計約670億円の削減額と削減幅は、いずれも戦後最大だった。
Q なぜ国は引き下げたの?
A 国は「08~11年に物価が4・78%下がった」とする厚生労働省の算定を根拠に、物価が安くなる「デフレ」の調整が必要だとして引き下げを決めた。自民党が、12年末の衆院選の公約で「生活保護の給付水準の原則1割カット」を掲げ、政権に復帰したことも背景にあると言われている。
Q 受給者が訴えていることは?
A 兵庫県の受給者たちは、食費を削ったり電気代を節約したりして苦しい生活を強いられているとして、引き下げは生活保護基準を定めた生活保護法8条や憲法25条に違反すると主張。神戸市など4市に対し、減額決定の取り消しを求めている。
Q 各地で裁判が起こされているの?
A 同じような裁判は全国29カ所で起こされ、6地裁で判決が出た。名古屋(昨年6月)、札幌(今年3月)、福岡(同5月)、京都(同9月)、金沢(同11月)の5地裁は、基準額の引き下げは厚労相の裁量の範囲内として、原告側の訴えを退けた。一方で、大阪地裁は今年2月、国が基準額を引き下げた判断過程に誤りがあるとして、減額決定を取り消した。引き下げを憲法違反だと判断した判決はない。
Q 神戸地裁判決の注目点は?
最大の争点は、基準額の引き下げが厚労相の裁量の範囲内といえるかどうかだ。受給者側は、専門家の意見をふまえずに引き下げを決めた厚労相の判断は裁量権を逸脱していると主張。被告側は厚労相には幅広い裁量があると反論し、引き下げは適法だと訴えている。生活保護費は、医療や福祉、教育といった多くの制度と連動している。引き下げが違法や違憲と判断されれば、こうした制度の運用や国の政策に影響を与える可能性がある。