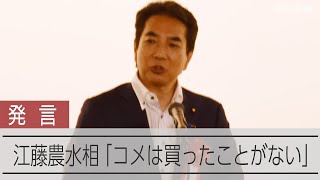常総水害を語り継ぐ 被害から6年、住民が記録誌 教訓を共有したい
【茨城】災害関連死を含めて15人が亡くなった常総水害は、10日で丸6年を迎えた。被災した住民らはこの日に合わせ、被災の記憶や生活再建までの道のりをつづった記録誌を発刊した。増え続ける豪雨水害の被災地にも教訓を共有したい、という思いを込めた。
記録誌は「常総市大水害の体験を語り継ぐ 被害者主人公の活動 6年の軌跡」。
被災直後から生活再建などの要望活動を続けてきた茨城県常総市の住民ら12人が編集委員を務めた。河川管理の問題を指摘し、国を訴えた賠償訴訟の原告もいる。昨年1年間かけて、被災した住民に聞き取った体験談や、寄稿文を集めた。
2015年9月10日、鬼怒川の7カ所で川の水があふれ、堤防が約200メートルにわたり決壊。市面積の3分の1に浸水が生じた。約4300人が自宅などに取り残され、自衛隊や消防に救助された。
同市原宿の高橋敏明さん(67)は、川の水があふれた地点から約1キロの場所で、植物の栽培や販売をしていた。16棟あった温室と店舗は高さ1メートルの泥水につかり、育てていたパンジーやポトスなど約10万株が流失した。商品や設備の被害は5千万円を超えた。再建のため多額の借金をしたことで赤字経営が続く。「手塩にかけた花は娘のようなもの。それが一瞬にしてなくなってしまった」
妻がプライバシーのない避難所生活で体力を奪われた末に死亡し、ショックでうつ病になった男性も体験談を寄せた。農機具が土砂に埋もれ、先祖伝来の家業を断念した農家も。生活の営みを奪われた困難だけでなく、事業を再開して全国から駆けつけたボランティアへの感謝の思いも記されている。
必要な支援を国や県に働きかけ、実現する過程も書きとめた。住宅の被害が大規模半壊以上の世帯に限られていた支援金は、被災後に住民や区長、県議らが働きかけたことによって、半壊世帯にも支給の枠が広がった。編集委員の染谷修司さん(77)は「被害者が嘆くだけでなく、声を上げ続けることが大切。ほかの被災地の方々にも伝えたい」と話した。
市内には日系ブラジル人なども多く暮らす。横田能洋さん(54)は、被災直後、必要な情報をポルトガル語などに翻訳してラジオや情報誌で発信した経験を記した。
19年の台風19号で深刻な被害を受けた県北地域の被災者世帯に、独自にまとめた常総の被災体験記を配って歩いた。受け取った1人は感想とともに「これを読んで家の再建を決めた」と、決意を報告してくれた。「絶望した被災者は、制度の内容を説明した資料を読んでもすぐ動けない。現在、苦しんでいる各地の被災者がかつての被災者一人ひとりの思いを知ることは大きな励みになる」と意義を語った。
記録誌は500円。希望者は染谷さん(kinusoshu@outlook.jp![]() )へ。
)へ。
◇
常総市上三坂地区の鬼怒川の堤防決壊現場では10日、亡くなった住民をしのび、神達岳志市長や地元の住民らが献花し、黙禱(もくとう)を捧げた。献花を終えた後、神達市長は記者団に「住民の死をむだにせず、防災に取り組むのが責任」と語り、住民の防災意識の向上に注力する決意を語った。