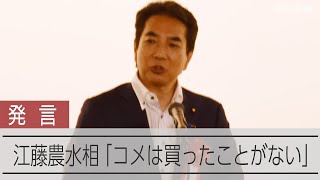「まちの書店」を取材 三宅玲子さん寄稿
コロナ禍で増えた「おうち時間」、本に親しんでいる人も多いのではないでしょうか。ネットで本を注文するのが当たり前になっている昨今ですが、鳥取では「まちの書店」が息づいています。各地の書店を取材し、鳥取大医学部付属病院広報誌「カニジル」でも執筆しているライターの三宅玲子さんに、鳥取の書店の系譜について寄稿をいただきました。
◇
カニジル。この風変わりなタイトルの冊子は、鳥取大学医学部付属病院の広報誌だ。広報誌といっても、実際には医療現場で奮闘する人たちの実像を伝えるノンフィクション誌と言った方が正確だろう。編集長でノンフィクション作家の田崎健太さんのもと、私は昨夏から編集チームに参加しているのだが、編集長に誘われたとき、喜んで!と応じたのには伏線がある。
昨年1月、私は鳥取市に定有堂書店を訪ねていた。日本各地の独立書店を訪ねるウェブ媒体での連載の取材だった。
定有堂書店は全国の書店員の「聖地」と呼ばれる。思想、哲学から文芸、映画まで、店主・奈良敏行さんが趣向を凝らして編集した棚は魅力があった。
だが、私が何より心を奪われたのは、奈良さんが定有堂を舞台に紡いできた鳥取の本読みたちとの交わりの物語だった。若い時期の人生への煩悶(はんもん)を経て、1980年に奈良さんは東京から鳥取に移り住んで書店を始めた。
すると開店初日、老舗書店の店長が花束を抱えて訪れ「仲間が増えてうれしい、困ったことがあったらなんでも言ってくれ」と祝った。ある本読みの客は「本好きが始めた本屋だから期待しているんだ」と、具体的な出版社名を挙げて取り扱う本を助言した。一人の高校教師の発案で始まった読書会は、今年で33年になる。
本を通して心を開き合う鳥取の人たちをもっと知りたい。奈良さんの話を聞いて以来、私はそう思うようになった。
その鳥取で、腕の立つノンフィクションの書き手が編集長としてメディアをつくる。ここにはしっかりと取材された読み応えのある物語を歓迎する本読みがいると直感的に思った。カニジルに参加を決めたのは、定有堂を通して鳥取にすでに惹(ひ)かれていたからだ。
本屋との出会いはさらに続く。奈良さんに勧められ、湯梨浜町に「汽水空港」を訪ね、心底驚いた。人口1万7千人の町で、思想や経済学、文学、芸術の新刊と古書など、人生の伴走者のような本だけを並べる美しい小さな本屋が成り立っていたのだ。店主モリテツヤさんは34歳。組織などのシステムから距離をとった生き方を模索し、自給自足しながら書店を営んでいる。モリさんに共振する人たちが半径100キロ圏内から訪れる。
本が売れない時代に定有堂や汽水空港のような個性の強い書店が鳥取に存在する。「これは偶然ではないんですよ」と奈良さんが言うので、さらに驚いた。鳥取には書店を育てる土壌があり、土壌を育んだのもまた書店だというのだ。
そして私は地域の発展のために私塾を開いたことがきっかけで明治5年に書店をつくった医師を知った。勉学のための書物を取り扱ったことから始まった今井書店の創業者・今井兼文だ。今、山陰地方で19店舗を展開する今井書店は、昭和期には書店組合の連帯を牽引(けんいん)し、地域図書館の普及に貢献した。定有堂の初日に花束を届けた人物は、玄孫で現相談役の永井伸和さんだ。永井さんは汽水空港のモリさんを孫のように目配りする。
鳥取の書店の物語に心奪われ、5月発行予定のカニジル最新号では「本の王国 山陰を歩く」をルポした。
本屋は人に出会う場所でもある。定有堂書店から教わったことだ。
◇
みやけ・れいこ 熊本県出身。近著に「真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園」(文芸春秋)。ニッポンドットコムにて「たたかう『ニッポンの書店』を探して」を連載中…