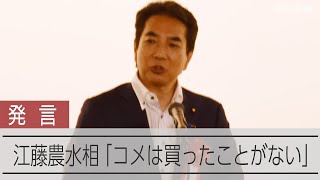潰瘍性大腸炎などの薬、胎児に影響の可能性 動物実験で
潰瘍(かいよう)性大腸炎などに使われる薬「チオプリン」が、胎児の遺伝子の型によっては、悪影響を及ぼす可能性があることを、滋賀医科大と東北大の研究グループが動物実験で見つけた。今後、ヒトでの影響がないか調べていくという。
チオプリンは腸の病気や急性白血病などの治療に長く使われ、安価で効果があることがわかっている。ただ、患者の「NUDT15」という遺伝子の型によっては白血球が減少する副作用があり、薬の使用前に患者の遺伝子型を調べることが勧められている。医学生物学研究所と東北大が開発した検査キットが使われている。
チオプリンが母親には副作用が出ない量だった場合も、胎児に及ぼす影響についてはわかっていなかったため、グループは、胎児の遺伝子型による影響を調べることにした。
遺伝子型は、父と母から伝わった遺伝子のペアがいずれも副作用を受けない「正常型」、片方が副作用を受けるタイプの「ヘテロ型」、両方が副作用を受ける「ホモ型」に分けられる。
グループは、遺伝子操作でヒトと同じNUDT15遺伝子が働くようにしたマウスで、妊娠中にチオプリンを使った。すると、ヘテロ型のメスとオスからは、ホモ型の子が25%産まれると推定されるが、産まれなかった。正常型のメスとヘテロ型のオスの場合、半数がヘテロ型の子になると推定されるが、産まれなかった。
こうした結果から、母親には副作用が出ない量でも、胎児の遺伝子型によっては、死亡する可能性が示された。薬によって血液の細胞をつくる造血幹細胞が減少したことが原因とみられた。
チオプリンで症状が安定している場合、他の薬に切り替えることは、症状を悪化させるリスクがあるため、今回の結果で、すべての妊婦の使用禁止を提案するものではないという。
滋賀医科大の河原真大講師は…