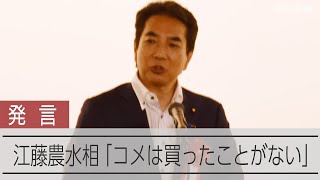最近の朝日、行儀良すぎ 池上彰の新聞ななめ読み最終回
池上彰の新聞ななめ読み(最終回)
何事にも始まりがあれば、終わりもあります。14年間にわたって本紙に連載してきた当コラムは、今回をもって終わります。今回は朝日新聞の提案により、読者へのあいさつの機会をいただきました。
単に「これで終わりです」と書くと、疑念を生じてしまうのが、このコラムの宿命だからです。そこであえて説明しますが、コラム終了は、朝日新聞社側の要請ではありません。私自身が70歳を超え、仕事量を減らす一環としての決断です。
仕事の引き際とは、難しいものです。いつまでも働けることはありがたいことです。でも、誰にも老いはやってきます。老いの厄介なところは、自分の思考力や表現力の摩滅に自身は気づきにくいということです。いつの間にか、私のコラムの切れ味が鈍っているのに自身が気づかなくなっているのではないかという恐れから身を引くことにしたのです。いや、そもそも切れ味などなかったと言われるかもしれませんが。
そもそものコラム開始は、2007年4月でした。当時の朝日新聞東京本社夕刊編集部の求めによるものです。「いろんな新聞を読み比べる論評を毎週執筆してほしい。何を書いても自由で、内容に関して注文はつけません。朝日新聞の記事の批判も歓迎します」というものでした。なんと太っ腹なことか。朝日新聞の余裕を感じさせましたね。
コラムのタイトルは、どうするか。私の提案で「新聞ななめ読み」と決まりました。たくさんの新聞を読むために、ざっと「ななめに読む」こともあるし、新聞記事を「斜に構えて」論評することもあるだろうから、という趣旨です。
毎週月曜日の夕刊に掲載が始まりましたが、大阪本社は掲載しませんでした。大阪本社は、東京本社とは編集権が別だからです。
その結果、広島の知人から「こっちの朝日にはコラムが載っていないぞ」と言われることもありました。広島は大阪本社管内です。東京本社が絶対的な力を持っているわけではないことを知り、さすがに大阪発祥の新聞だけのことはあると感心しました。
それはともかく、書くテーマの多くは「朝日新聞の記事が難しすぎる」というものでした。とりわけ経済記事では多く、日本の不動産投資をめぐって「イールドギャップ」という金融用語をそのまま使っていることを批判したこともあります。経済専門紙なら許される表現でも、一般紙は避けた方がいいのではないかという批判を繰り返し展開してきました。
ときには批判の対象になった記事の担当デスクから反論が寄せられ、それへの再批判も合わせて次の週のコラムで取り上げることもしました。
そのうちに、〈朝日新聞の記者は月曜日の夕刊では真っ先に「新聞ななめ読み」に目を通す〉と言われるようになったそうです。自分の記事が俎上(そじょう)に載っていないか気になってのことでしょう。
このコラムは10年3月まで続きましたが、毎週テーマを決めて新聞記事を論評するのは大変な重労働です。そこでやめさせてほしいとお願いしたところ、それでは朝刊のオピニオン面で月1回のコラムとして継続しないかと声をかけていただきました。それなら負担も減ると考え、提案をお受けしました。今度は大阪本社版でも掲載されることになりました。
ところが、14年8月、事件が起きました。朝日新聞が過去の従軍慰安婦報道を検証する特集記事を掲載することになったので、コラムで取り上げて欲しいと要望されたのです。これまでコラムで取り上げるテーマについて注文がつくことはなく、珍しいことではあったのですが、大事なテーマであるだけに、論評することを承諾しました。
朝日の検証記事は、過去に朝日が報道した「済州島で200人の若い朝鮮人女性を『狩り出した』」という吉田証言が虚偽であることを認め、これを報じた朝日の記事を取り消したものです。
これについて私は、なぜ32年間も訂正しなかったのか、間違えを認めたら謝罪すべきではないか。検証すること自体は評価するが、遅きに失したのではないかと批判するコラムの原稿を送りました。
すると、このコラムの掲載を朝日新聞社の上層部が認めず、掲載されなかったのです。
言うまでもなく新聞に何を掲載するかの編集権は新聞社にあります。私がどうこう言える立場ではありません。しかし、「自由に書いてください」と言われて始めたコラムの内容が気に食わないからという理由で掲載されないのでは、信頼関係が崩れます。そこで私は「掲載するしないは新聞社の編集権の問題ですから、私は何も言いませんが、信頼関係が崩れた以上、コラムの執筆はやめさせていただきます」と申し入れました。
これはあくまで私と朝日新聞社との間の問題であり、私は誰にも口外しなかったのですが、「週刊新潮」と「週刊文春」の知るところとなって報道されました。私のコラムの掲載が認められなかったことを知った朝日新聞社内部の誰かが週刊誌に伝えたのでしょう。
ここから私は嵐に巻き込まれました。各メディアからの取材攻勢を受けたのです。
これをきっかけに、ライバル紙や週刊誌などからの朝日新聞バッシングが始まりましたが、驚いたことに、朝日新聞の記者たちが、次々に実名でツイッターに自社の方針を批判する投稿をするではありませんか。
実名で自社の方針を批判するのは勇気のいることです。自社の記者にツイッターへの投稿を禁止する新聞社もある中で、記者たちに言論の自由を許している朝日の社風に感銘を受けました。多くの記者たちの怒りに励まされる思いでした。
こうした社内の記者たちの怒りの声に押され、朝日新聞は誤りを認めて、私のコラムは掲載されました。
しかし、この騒動で朝日に愛想を尽かした読者もいたようで、朝日の購読者数が大きく減るきっかけになりました。
このときは皮肉なことに、朝日たたきに走ったライバル紙も部数を減らしました。朝日新聞を批判するチラシをつくって各戸に配布し、自社の購読を勧める新聞社も出てきたほどですから、連日のように朝日を批判する記事を読まされ、動機が不純だと不快に思った他紙の読者もいたのでしょう。
結果、新聞業界全体に打撃を与えることになりました。
この嵐の中で、私は朝日新聞の自浄努力を注視していました。新聞社の「編集権」は誰が行使するのかを明確にしたり、社の内外からの批判を紙面づくりに生かす仕組みを構築したりと、社内の改革の努力を始めていたからです。
その後、朝日は記事内容を社の内外の人たちがチェックするパブリックエディター制度を導入しました。
また、記事の訂正もどんどん掲載するようになりました。ここで注目すべきは、単に「訂正します」ではなく、なぜ誤報をしたのか、その理由まで記すようになったことです。
私もNHKで32年間にわたって記者をしてきましたから、間違いを訂正することが、どれだけ恥ずかしく、また勇気がいることかよくわかります。それでも誤報を知らん顔せずに率直に訂正記事を掲載することになったのは、大きな進歩だと思います。
朝日は大きな間違いを犯しましたが、誤りを認め、二度と誤りを繰り返さない体制づくりを進めたことを評価し、私は連載を再開することにしました。再開を喜んでくださった読者が大勢いると聞いたことは、その後の執筆の励みになりましたし、重圧にもなりましたが。
こんなことがあったものですから、その後、私としてはコラムの執筆をやめると言い出せず、ここまで来てしまいました。
掲載拒否騒動から6年半。その後の朝日の紙面を見る限りでは、なんだか“お行儀”がよくなり過ぎた気がします。外部からの批判に耳を傾けることは必要ですが、気にし過ぎると、批判すべき対象への批判の矛先が鈍ったり、何が何でも特ダネを取るのだという意欲が薄れてしまったりする恐れがあるように思えます。
最近の総務省の会食接待問題をめぐる「週刊文春」の特ダネ連打を見ると、新聞社は何をしているのだと苦情を言いたくもなろうというものです。
「週刊文春」が何者にも忖度(そんたく)しないで特ダネを連発してきた結果、編集部にさまざまな情報が集まるようになっていると聞きます。新聞社だって読者の信頼を得られれば、もっと情報が寄せられるのではないでしょうか。
「週刊文春」に特ダネを連発されてしまうことを屈辱と考えて頑張ってほしいのです。
今月で私のコラムは終了しますが、新聞各社の記者諸氏は、どうか記者としての矜持(きょうじ)を大事にしながら、常に自分の記事を読者の視線で点検することを忘れないでほしいと思います。コラムは終わっても、私の「新聞ななめ読み」は続きますから。
◇
1950年生まれ。NHKの報道局記者や番組キャスターを経て2005年からフリーに。名城大学教授や東京工業大学特命教授も務める。