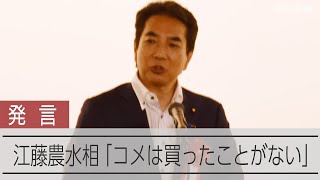核廃絶の訴え♯拡散願う 長崎市長×高田明さんが対談
核兵器禁止条約の発効を記念し、東京と広島、長崎を結んで23日に開かれたオンラインイベントには、条約実現に尽力した被爆者や支えた人たちが参加し、海外からもメッセージが寄せられた。核廃絶への大きな一歩を喜ぶとともに、次の一歩の課題を語り合った。
◇
長崎会場の長崎原爆資料館(長崎市平野町)では、通販大手「ジャパネットたかた」の創業者・高田明さん(72)と田上富久市長が対談。核禁条約についてより多くの人に興味を持ってもらうにはどうすればいいかを語り合った。
高田さんは「条約を知る入り口は必ずしも戦争や原爆じゃなくていい」。7年前、ALS(筋萎縮性側索硬化症)への支援を行動で示す「アイス・バケツ・チャレンジ」がSNSで広がったことを例に挙げ、今後の平和活動にはキャッチーさも必要だと提案した。
田上市長は「核兵器廃絶の訴えの原点は被爆者が語ってきた被爆体験だ」としつつも、「伝え方は変えていかないといけない」と応じた。この1年、若者を中心にオンラインイベントの開催やSNSでの発信が活発になったことを挙げ、「被爆100年までの期間は、いろんな伝え方を試して、平和活動を進化させないといけない」と語った。
被爆者や高校・大学生6人も、条約発効に寄せて思いを語った。すべての国に条約への参加を求める「ヒバクシャ国際署名」の長崎での活動をリードしてきた朝長万左男さん(77)は「被爆者は高齢だとはいっても、まだまだ生きる人もいる。条約の加盟国・地域を増やすためにこれからも運動する」と決意をあらたにした。核兵器廃絶に取り組む学生団体「ナガサキ・ユース代表団」の大園穂乃佳さん(19)は「条約発効が、『核兵器による安全保障は正しいのか』と考えるきっかけになれば。同世代の人たちに問題意識を発信していきたい」と話した。
この日、東京でイベントを司会した林田光弘さん(28)は長崎出身の被爆3世。高校生平和大使OBで、「ヒバクシャ国際署名」ではキャンペーンリーダーを務めた。締めくくりに、こう述べた。「これから『核兵器なき世界』を実現するためのたくさんのアイデアが話された。まずは今日からできることを、ともにやっていきたい」
湯崎英彦知事や松井一実市長も参加した広島会場からは、若者たちがそれぞれの「平和活動」について発表した。
広島市立舟入高2年で演劇部の高橋遥香さん(16)は、昨年11月に上演した原爆劇で脚本を担当した。原爆ドームとその保存活動に取り組んだ人々を描いた。
被爆者の高齢化で「物言わぬ証人」としての被爆建物の価値は高まっているとし、現在、保存・解体問題で揺れている被爆建物「旧陸軍被服支廠(ししょう)」について考えるきっかけになってほしいとの思いで制作したと報告した。「同じ空気を共有できる舞台演劇では、演じる側も見る側も、原爆ドームの保存運動に取り組んだ人々の思いとその時代を疑似体験できる」
NPO法人「ANT-Hiroshima」のインターンで広島大4年の赤井理子さん(21)は、被爆者が日常生活で悲惨な体験を思い出す瞬間をイラストにしてインスタグラムで発信しており、その中で抱いた思いを語った。被爆者の岡田恵美子さん(84)から、夕焼けを見ると炎から逃げた当時を思い出すという証言を聞き、夕焼けをイラストに描いた体験から、「証言は今の日常が当たり前ではないという想像力を与えてくれるもの。76年前の記憶と私の暮らしをつなげようと表現している」と述べた。
広島市立基町高3年の原田真日瑠(まひる)さん(18)は、被爆証言をもとに当時の様子を描く「原爆の絵」の制作について発表した。赤井さんの取り組みについて「『相手の立場に立って描く』という言葉が印象的で、その姿勢は原爆の絵を描く時にも心掛けたい。絵を描くという表現方法は一緒だが、今を生きる日常と結びつける視点は新鮮だった」と話した。
イベントの録画は、主催団体の一つ、「核兵器廃絶日本NGO連絡会」のホームページ(https://nuclearabolitionjpn.wordpress.com/![]() )で視聴できる。
)で視聴できる。