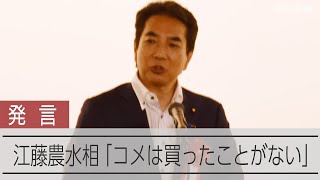核禁条約批准を 山口県内議会では採択ゼロ
核兵器禁止条約(核禁条約)が22日に発効した。条約を批准していない日本政府に対し、全国各地の地方議会で意見書や決議で批准を求める動きが相次いでいるが、山口県内では同様の意見書や決議を採択した議会はない。被爆者や支援を続けてきた人たちは複雑な思いを抱いている。
県内19市町の議会と県議会に、核禁条約への批准を政府に求める意見書や決議案が採択されたかどうか、朝日新聞社が聞いた。
下松市議会では2017年9月、国に条約の批准を求める議員提案があったが、賛成少数で否決された。議事録によると、一般質問で核禁条約への見解を問われた国井益雄市長は「外交、防衛に関する事項で、見解を述べる立場でない」と述べた。山口市議会でも17年12月、同様の議案が否決。山口、周南、萩の3市では、市民から陳情や請願が寄せられたが、いずれも採択されていない。
核禁条約とは別に、09~10年には県議会や下関、長門、周南、岩国の各市と阿武町で、核兵器の廃絶や恒久平和を求める意見書が採択された。当時は10年の核不拡散条約(NPT)再検討会議が背景にあった。
原水爆禁止日本協議会の集計によると、22日時点で全国の自治体議会の30%にあたる528議会で核禁条約についての意見書や決議が採択されている。採択がゼロの都道府県は、山口のほかに富山、福井、佐賀の3県のみという。
県によると、県内で被爆者健康手帳を持つ人は、昨年3月末時点で2205人いる。人口比では全国でも多い。
村岡嗣政知事は21日の記者会見で「核兵器廃絶を求める多くの思いが広がり、実現に至ったと思う。ただ核保有国と非保有国が認識を一つにしなければ(核廃絶が)進まないのも現実。(批准しようとしない)政府の考え方を尊重する」と語った。
山口市の大内人形職人小笠原貞雄さん(94)は、広島への原爆投下後、旧陸軍被服支廠で救護活動をして被爆した。「あのみじめな現場を見た被爆者の思いは山口の議員にも通じていると思っていた。受け止めてもらえるよう訴えていきたい」と話した。
山口井筒屋前では22日午前、原水爆禁止山口県協議会などが日本政府に核兵器禁止条約への賛同と批准を求める署名を呼びかけた。条約発効を歓迎する横断幕と、政府に批准を求める横断幕が並んだ。
県原爆被爆者支援センターゆだ苑の岩本晋理事長(78)は「被爆者の願いがかなう第一歩の日。被爆者支援を続けてきた立場で言えば、県民の代表である知事をはじめ政治家の方々には先を見てできることを一つでも多くしてほしい」と残念がった。
◇
22日に発効した核兵器禁止条約は、核兵器を全面的に違法とする初の国際法だ。被爆者で、山口県原爆被害者団体協議会副会長の村上暢英(のぶひで)さん(76)は「やっと一歩前進。ただ、世界で唯一の戦争被爆国である日本が批准しないのは腹立たしい」と政府に厳しい視線を向ける。
1歳4カ月の時に被爆した。爆心地から2・5キロ圏内の広島市内に母と姉、祖母と暮らしていた。全員大きなけがはなかったが、下松の軍事工場に勤めていた父も入市被爆した。
被爆の記憶はない。半年ほど経った後、へんとうが腫れ、左耳がよく聞こえなくなった。
4歳から山口市内で暮らす。常に自分が被爆者だと意識してきたわけではない。だが、「いつも心の中にわだかまりがあった」と村上さん。結婚し、子どもが生まれた後も、病気や遺伝の不安は消えなかった。
「核兵器は人の人生を狂わせる。こんなこと二度と起きちゃたまらん」
70歳になり、自分にできることから始めようと、核兵器禁止条約への参加をすべての国に求める「ヒバクシャ国際署名」を個人で集め始めた。親族の集まりや同窓会、常に署名の紙を持ち歩いた。
約5年で集まった署名は300を超える。
「自分に出会って知ってくれた人から、少しずつでも平和の意識が広がれば」。日本が批准国になるまで、これからも平和への活動を続ける。
◇
長崎大核兵器廃絶研究センター・中村桂子准教授の話 80年代に各地で進んだ非核宣言のように、自治体や地方議会は「外交や安全保障は国の専管事項」という考えにあらがう形で反核の声を上げてきた。核を持つ米国では、州や都市が政府に批准を求める動きがある。核禁条約の影響力が世界で強まろうとする中、日本でも自治体の役割は大きくなるだろう。声を上げても国の政策は急には変わらないが、国への圧力になり、自治体同士が連携すれば国際的にも強いメッセージになる。山口県内で声が上がっていないのは残念でもったいない。議会は賛成や反対にとどまらず、当事者意識を持って活発に議論をすることが必要だ。
核禁条約には実効性がないとの声があるが、核に悪の烙印(らくいん)を押すという規範的効果がある。3年前に条約が採択された際に被爆者のサーロー節子さんが「核兵器の終わりの始まり」と話したように、発効は今後にとって重要な局面。私たちがどう活用していくかが問われている…