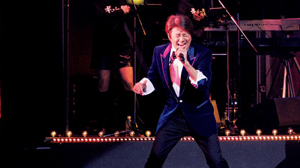民事にTeams導入、裁判官は「新鮮」 感染対策にも
水戸地裁(茨城県水戸市)は民事裁判の争点を整理する手続きなどで、裁判所と弁護士事務所などをインターネットでつないで話し合う「ウェブ会議」を14日から導入した。当事者が裁判所に来る負担を減らし、迅速に審理を進めるのが狙いだ。
「原告代理人は証拠を画面で共有してください」
阿部雅彦裁判官がこう語りかけると、双方の代理人が映った画面が事故状況図に切り替わった。11日、水戸地裁で報道陣に公開された模擬手続きの様子だ。
交通事故の損害賠償を争う訴訟の争点整理手続きを想定した。原告側は「原告の過失はなかった」、被告側は「原告の過失は6割を下回らない」と主張し、すぐに書記官がチャットに書き込んだ。
阿部裁判官は「民事訴訟は書面のやりとりが基本なので、画面で証拠を見るのは新鮮だった。顔をみてやりとりでき、争点整理にも役立つ」と期待を語った。
これまでも当事者が遠隔地にいる場合などに電話での手続きは認められていた。だが、どちらか一方は裁判所に足を運ばねばならず、顔が見えない問題もあった。水戸地裁は都内など県外から来ている弁護士も多く、ウェブ会議は新型コロナの感染対策にもつながる。
最高裁広報課によると、ウェブ会議の導入は2月に東京地裁などではじまり、10月までに13地裁と知財高裁で約1万1千件行われてきた。オンライン会議システム「Teams」を使い、多要素認証などのセキュリティー対策を取っている。これまで目立ったトラブルはなく、裁判官からも「利便性が高い」と好評だという。
14日からは水戸地裁を含む全国の地裁本庁で導入され、来年度以降は支部でも導入が検討されている。
一方、現在の民事訴訟法は「書面」と「対面」が原則のため、ウェブ会議が使えるのは和解協議手続きなど一部に限られ、口頭弁論は法廷で行われる。
将来的には法改正を経て口頭弁論でのウェブ会議の運用や、システム開発を経てオンライン上での訴状の提出も検討されているという。ウェブ会議の導入が裁判のIT化の第一歩となるかが注目される。