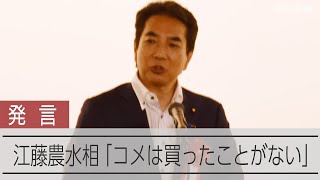日本の童謡、4分の1以上が冒頭に花鳥風月 調査で判明
心に響く歌の豊かさには、日本の自然が大きな役割を果たしていた――。国内の研究チームが、童謡や唱歌約1万3千曲の冒頭の一節を調べたところ、山や森、桜、蛍など身近な自然や生き物が、全体の4分の1以上に含まれ、文化的な創作活動に影響していたことがわかった。
「ゆうやけこやけの あかとんぼ」(三木露風作詞「赤とんぼ」)、「うさぎおいし かのやま」(高野辰之作詞「故郷(ふるさと)」)、「さくらさくら やよひのそらは」(日本童謡「さくらさくら」)……。学校で子どもに歌い継がれてきた童謡・唱歌には、自然豊かな日本の原風景のイメージがたびたび現れる。
そんな歌に注目した農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の研究チームが5月、研究成果を生態系に関する国際学術誌エコシステムサービス(https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101116![]() )に発表した。
)に発表した。
チームは国立(くにたち)音楽大学付属図書館の「童謡・唱歌索引」で調べられる、1万2550の童謡・唱歌の冒頭の一節を分析。ほとんどの歌は、義務教育が始まった1872年から、終戦の1945年までに作られたとみられる。
歌詞に、海、森、農地といった日本の主な生態系や、生き物に関わる単語が含まれているかどうかを調べた。例えば、森であれば、「モリ」のほか、「ハヤシ」「ヤマ」といった単語があらわれた場合にカウントした。
生き物は、植物、虫、鳥といった区分のほか、「バラ科」など、科別にも集計した。「故郷」の1節目であれば、「ウサギ」と「ヤマ」が登場するので、「森」「哺乳類・ウサギ科」に数えるといった具合だ。
すると、生態系、生き物にかかわる単語がそれぞれ1315曲(10・5%)、2331曲(18・6%)で見つかった。全体の25%以上の曲にはいずれかが入っていた。うち、生態系では森が43・1%と多く、海(24・6%)、湖と川(9・3%)が続いた。チームは「日本は海に囲まれている上、山林が多くを占めているため妥当に見える」としている。生き物では、植物が54・7%と最多で、次いで鳥(26・0%)、昆虫(10・0%)だった。
■サクラやウメ、スズメ、カラ…