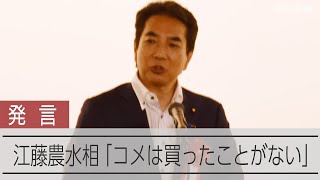(社説)日中条約45年 官に頼らぬ絆 より太く
日中平和友好条約が発効して45年。東京と北京では記念行事も催されたが、祝賀ムードとはほど遠い。台湾問題や半導体貿易規制をめぐる対立。東京電力福島第一原発の処理水放出を受けた水産物禁輸。難題は山積みだ。
日中の関係を政府間に限らないで、もっと広くとらえてみてはどうだろう。
日本の民間シンクタンク「言論NPO」が最近発表した、日中共同の世論調査の結果は注目に値する。
中国側は処理水放出を「大変/ある程度心配している」との回答が全体の半数近くを占めた。だが、「全く/あまり心配していない」が計26・7%、「現時点で判断できない」が25・0%もあった。
実際、中国には処理水放出に反発して日本に抗議電話をかける者がいれば、中国国内の放射能問題を指摘する者もいる。政府の強硬姿勢とメディア統制下においても、中国社会が健全な多様性を保っていることに留意したい。
10月上旬の国慶節休暇の前に中国の大手検索サイトなどが発表した人気の海外旅行先で、1位は日本だった。団体旅行にキャンセルがあったとはいえ、それでも多くの中国人が来日した。本国では食べられない魚介類を日本で楽しんだ人も少なくあるまい。
日中文化の結びつきを示す新たな動きもある。8月、東京・銀座に単向街書店が進出した。中国の作家、許知遠さんらが創設した書店で、東京が海外第1号店だ。日本の書籍の中国語訳が棚の多くを占める。谷崎潤一郎、東野圭吾から建築家の隈研吾の作品まで関心の幅広さに驚く。
ほぼ毎週、小規模の講演会を開く。日中を含むアジアがつながる文化空間を目指すという。中国人客が多いが「中国をもっと知りたい日本人も多い」と、書店代表の松本綾(あや)さんは手応えを語る。
一方、日本から中国への人の流れは細っている。日本学生支援機構によると、一昨年度に中国から来日した留学生は11万人を超えた。だが同年度の日本から中国への留学生は54人。コロナ禍前の多い年でも約8千人だった。
中国で「スパイ」対策が強化され、日本人が訪中に二の足を踏むのは理解できる。ただ、嫌中感情はそもそも中国を知らないためであることが多い。観光で来日し、日本を知る中国人が増えるにつれて中国社会の対日感情が改善したことを思い起こしたい。
双方の市民の相互理解は二国間関係の強固な基礎となるはずだ。政府間の関係がぐらつきがちだからこそ、その重みは増している。