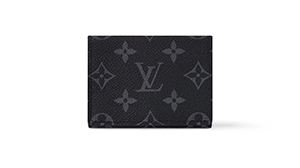(フォーラム)嫁、主人、家はいま:1 結婚式まで
結婚にまつわるモヤモヤ、話してみませんか。アンケートで呼びかけると、結納など従来のしきたりや結婚式の定番の演出に違和感がある、という声が寄せられました。ただ、変化も生まれているようです。
■形式より意義、自由な式 結婚情報サービス「ゼクシィ」編集長・日置香那子さん
どんなタイプの結婚式を挙げているのか、ゼクシィが昨年調べたところ、教会式が51.7%、招待客の前で結婚を宣言する人前式が28.5%、神前式が17.4%でした。10年前に比べて大きく変わっていません。ただ、演出内容はかなり自由になっていて、「形式的なもの」から「意義重視」への変化が昨今の特徴です。
例えば、ホテルや式場ではなく思い出の山や浜辺で挙げる▽レンタルドレスを着ずに、母親に譲り受けたワンピースにデニムジャケットを合わせる▽カップルが座る高砂を設けずに、招待客と一緒に座って交流を楽しむ、といった具合です。
招待客も付き合い程度の親戚や仕事関係者は減る傾向にあります。以前は人間関係の亀裂を懸念したものですが「招待客にとっても楽しい時間になるか」を軸に考えている人が多い。引き出物は、カタログギフトや食器類を全員に配るのではなく、一人ひとりに合わせて別々のギフトを選ぶ、という例もあるようです。
この変化は、結婚式が、女性が男性の「家」に「お嫁に行く儀式」という意識より「家庭を作る2人のけじめの場」という意識が強まっていることも背景にあると思います。一昔前は新婦だけが両親に「育ててもらったお礼の手紙」を読んでいましたが、最近は新郎・新婦ともが読んだり、手紙は読まずに新郎・新婦がそれぞれ招待客にあいさつを述べたりするケースもあります。
ただ「プログラムで決まっているから」ではなく、誰に何を語るべきなのかを考えて自分たち流にアレンジしています。
もちろん変わらない部分もあって、2019年度の調査では10%程度は結納をしていますし、披露宴の最後のあいさつは新郎側の父親がやるのが今も主流です。ただ、全体としては、結婚式はこうあるものという固定観念は薄れてきています。
ゼクシィでは最近、式場案内や披露宴に関する記事より、家事分担や将来設計といった新生活に関する記事が人気です。リアルな生活を考えている様子がみてとれます。2人にとっての「意義」を重視する傾向は続いていくと思います。
■男女や家、脱「固定観念」 フリーのウェディングプランナー・原田大二郎さん
昨年の夏まで結婚式場に勤め、プランナーとして多くのお客様の結婚式をプロデュースしてきました。
結婚式は基本的に、新郎・新婦の名前の並び順など、全てを男性から進めていく「男性優位」の形です。また、新郎からは「自分が養っていく」、新婦からは「ちゃんとごはんを作る」という意味を込め、お互いにケーキを食べさせ合う「ファーストバイト」や、父親とバージンロードを歩くといった、定番の演出もいくつかあります。
こうした式を挙げたいという需要も確かにある一方で、LGBTQの人や一般の男女カップルの中にも、「もっと自由に、自分たちらしい式を挙げたい」という希望があると感じます。従来の演出に違和感を持ち、「あそこには立ちたくないな」という気持ちを抱く人は、結婚式をしないことが多いのではと思います。
結婚式は「男女」や「家」に関する固定観念が、顕著に表れます。それは思い込みに過ぎないのに、式に来ている若い子や子どもにとっては刷り込みになってしまう。
私がウェディングプランナーを目指したのは、自分がゲイであるとカミングアウトした体験がきっかけでした。20代後半のころにすごく悩み、30歳を過ぎて、職場や家族に話しました。
振り返ってみると、私にとってカミングアウトは、「自分がどうありたいか」「どういう人生を歩んでいきたいか」を表現することでした。そうやって表現した自分を、周りのみんなは受け止め、認めて、祝福してくれました。
周りの人に認めてもらい、祝福される。これは結婚式にも通じることだと思ったんです。
いまは独立し、「Revolvo」というウェブサイトを立ち上げ、結婚式を挙げたいLGBTQカップルの相談を受けています。結婚式の計画を立てるときは、「2人はなぜ結婚式をしたいのか」をヒアリングし、生い立ちや仕事のことなども聞いてコンセプトを決めていきます。2人が歩みたい道が見えてくる、そんな結婚式にしたいと思いながら活動しています。
2人が対等であることをできる限り表現した結婚式を、2019年に京都府内のホテルで挙げました。従来の「しきたり」にのっとった結婚式の演出はしたくなかったので、夫と話し合って決めました。
その道のりは戦いの連続でした。
事前の打ち合わせで「全ての順番を男→女にはしたくない」と伝えると、プランナーの方は声も出ない様子で数秒固まってしまいました。新婦側の友人に出す招待状には私の名前を先に載せたかったのですが、式場側は「できません」。「せめて名前は横並びに」と交渉しました。
新婦は常に「下に置かれる」ことが「マナー」と感じました。
式では新郎側の親のあいさつの代わりに私たちがそれぞれスピーチし、2人が座る位置も途中で左右を変えました。司会者とは事前に打ち合わせ、「夫を支える妻」というような言葉は一切使いませんでした。
それでも結婚式をしようと考えたのは、私も夫も専門に研究しているフランス哲学の「脱構築思想」の影響です。批判したいものの内部にいったん入っていって、中から組み替えて、結局全体を変えてしまうという戦略を持った思想です。
「嫌だから結婚式をやらない」となれば、結婚式のシステムを変える一撃は打てなくなる。結婚式に関わる人や出席した人たちが考えるきっかけになればいいと考えました。
私たちは結婚式自体を単純に「セレモニー」とはとらえてはいなくて、ある種のマニフェスト(宣言)としてやりました。これからも関わっていく親族や友人、職場の方たちに「私たちはこういうスタンスなんだ」ということを最初に広く言っておくことによって、その後の関係性や生活にも影響があると思ったんです。
結婚式って「男尊女卑があるな」と気付くと、抵抗が出てくる。だけど私は、結婚式をやりたいならやってみればいいとアドバイスしたいです。その中で気になることや、どうしてもやりたくないことがあったら、変えられるところは変えてしまってもいい。折り合いをつけるためにどうしたらいいか。自分が式の中で実践してきたことなんだと思います。
■昭和の結婚観、根強い地域も 結婚相談所「マリーミー」代表・植草美幸さん
地域によっては「昭和の結婚観」が根強いところがあります。「嫁が男性の家に嫁ぐ」との意識があったり、妻は夫の親と同居するのが当たり前だと思っていたり。結婚する際に近所の人に「嫁を披露する」しきたりがあるところもあります。
地方に限らず、都会でも40代の男性が、夜勤があるという見合い相手の女性に「女のくせに夜勤があるの?」と驚き、女性から断られたケースもあります。専業主婦の母親を見て育った人が多いためでしょうか。
コロナ禍で変化もありました。大学を卒業したばかりの女性の入会が増えました。在宅勤務が続いて会社への帰属意識が感じられず、出会いも減ったことが背景にあります。
男性もコロナ禍で将来の見通しが立ちにくくなった現実を見て、「夫婦でしっかり働いていきたい」という人が増えました。「女性の方が収入が高いことをどう思うか」についても、約9割が「高くてもいい」「高い方がいい」と回答します。
■しきたりに違和感や怒り
アンケートに集まった声の一部を紹介します。そのほかの声もhttps://www.asahi.com/opinion/forum/139/で読むことができます。
●結納しない=父親は失業中?
結婚したとき、夫は学生、私は社会人。費用は親に頼らず貯金から、結納や盛大な披露宴はしないと決めた。夫の父親から「結納もしないなんてお宅のお父さん、失業しているの?」と言われ、あっけにとられた。(奈良県 50代女性)
●「お嬢さん頂く」に母が激怒
「立派に育てて頂き、素晴らしいお嬢さんを頂いて」と夫の叔母に感謝の言葉を向けられた母は内心、激怒。あげるために育てていない、物ではない、まるで猫や犬に向ける言葉だと、悔しがり悲しみ、怒っておりました。(東京都 50代女性)
●夫側改姓を「養子に入る」
私はパートナーに改姓してもらうつもり。両親は「養子に入る」と表したり、彼の両親よりも優位になったような気分だと言ったりする。彼の両親は結納を求めているが、私は人身売買をされているようで、結婚を祝福する行為だとは到底思えない。改姓や結納に皆が喜びを感じるわけではないことを知ってほしい。(東京都 20代女性)
●最後は思いやり
どんな考え、慣習もみんな同じなら問題は起きないが、「しきたり」を完全に無視することもいいとは思えない。権利は法で守り、文化は教育し、最後は思いやりか。(大阪府 50代男性)
●白無垢に違和感
結婚式の白無垢(むく)について「花嫁は今までの人生を真っ白にして夫との人生を進む」と式場の人に言われました。花嫁だけに求められ、花婿は今までの延長を歩むということに、違和感を感じました。(福島県 30代女性)
●婚約指輪の金額そんなに大事?
婚約指輪は、月給の何倍という「しきたり」の意味がわからない。男性がプレゼントするものとされているが、月給の何倍とかもうやめにしないか?(大阪府 40代男性)
●変化取り入れ家族大切に
日本は夫を中心とした家族で長らくうまくいっている。妻が働く機会が増え変化しつつあるが、親族を含む家族や地域の発展に繋(つな)がっているので、変化をうまく採り入れながら家族を大切にしたい。(東京都 50代女性)
◇5年前に出席した結婚式で、新婦のベールを母親がおろす「ベールダウン」というセレモニーを知りました。司会者の説明によると、「子育て終了の証し」だそうです。「子育てイコール母親なのか」「結婚しないうちはまだまだ子どもってこと?」。疑問は尽きませんでしたが、その時は「結婚式ってこういうものなのか」と自身を無理やり納得させました。
今回の取材を通じて、自分がモヤモヤしたのは、結婚式の演出の背景に「女性はこう、男性はこう」という固定観念があったからだと気付きました。「しきたりだから」「こういう決まりだから」。そうした言葉に黙らされず、背景にはどんな考え方があるのかを丁寧に問い続け、感じた違和感を周囲と共有することが大切だと、改めて感じました。(前田朱莉亜)
◆記事は、小林未来、田中聡子、前田朱莉亜、山本奈朱香が担当しました。
◇来週12日は「嫁、主人、家はいま:2 結婚したら」を掲載します。
◇フォーラムアンケート「出生前診断へのお考えをお聞かせください」をhttps://www.asahi.com/opinion/forum/で実施中です。