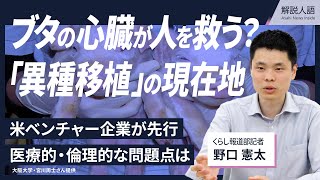障害ある人への「合理的配慮」 本当に必要なのは リロン編集部から
障害のある人が社会生活を送る際の障壁を、負担が過重にならない範囲で取り除く「合理的配慮」が、4月から民間企業にも義務化された。ただ、配慮を求める障害者へ反発を目にすることも少なくない。4月開始の特集「バリアーをなくすのは誰か」では「対話」を鍵に、この問題を考えている。
4月8日配信「車いすインフルエンサーが映画館で望む未来 悔し涙からの話し合い」は、車いすユーザーの中嶋涼子さんが映画館での悔しい出来事をSNS投稿して炎上したものの、映画館側と話しあえた経緯を紹介。障害のある当事者と、かかわる人とが「もっとコミュニケーションを」と語った。
4月22日配信「解消法は『障害者優遇』なのか 半世紀前の言葉が問う『発想の転換』」は、障害者の自己表現を研究する荒井裕樹さんの寄稿だ。ある障害者運動家の言葉を紹介しながら、障害者が「誰かからの『許容』や『許可』の範囲で社会参加する」という発想からの転換や、そのための対話と調整の必要性を訴えている。
5月2日配信「対話不足の『過剰な配慮』、障害者雇用の発展阻む コンサルが指摘」では、脳性まひがある障害者雇用コンサルタントの黒原裕喜さんが、雇う側の企業が「過剰な配慮」に陥る問題を指摘。対話を重ね、健常者側だけでなく障害者自身も自分の障害や特性を理解することで、働く環境を整えていく必要があるという。
反発を超え、壁をなくす過程にそぐうのは、「配慮」より対話を経た「調整」だと感じる。様々な人の声からさらに考えたい。(畑山敦子)…













![ニュースの要点[object Object]](http://www.asahicom.jp/imgopt/img/19c763907e/hd640/AS20240613004333.jpg)
![ニュースの要点[object Object]](http://www.asahicom.jp/imgopt/img/d44a92cf0b/hd640/AS20240612003868.jpg)
![ニュースの要点[object Object]](http://www.asahicom.jp/imgopt/img/39664562a9/hd640/AS20240611004419.jpg)
![ニュースの要点[object Object]](http://www.asahicom.jp/imgopt/img/2efd3dafdb/hd640/AS20240610003997.jpg)
![ニュースの要点[object Object]](http://www.asahicom.jp/imgopt/img/5341bd4e9d/hd640/AS20240609003465.jpg)