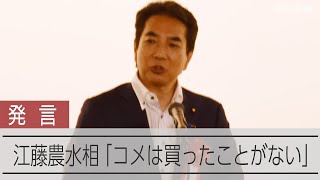地域の日常豊かにする情報を詰め込んで 600号超えの「月刊みと」
「編集長」は現場にいる。カメラを抱えて取材し、商品が完成したら書店へ配達にも行く。茨城県内の情報を発信するタウン誌「月刊みと」(水戸市)は、4人の女性たちで作り上げている。編集長の十津川(とつかわ)良子さん(59)も、その一人として、現場を大切にしている。
日立市で生まれ、親の転勤で幼少期から高校まで岡山で育った。茨城大学への進学を機に、再びなじみのある茨城に戻った。
卒業を控えた大学4年生の夏。就職活動をしながら月刊みとの存在を知った。「高校生のとき、編集者になりたいと思っていたな」。色々な場所に出かけて人との出会いがあることに期待を持った。編集部に電話をかけたものの、小さな出版社で定期採用はしていないという。しかしアルバイトとして働けることになり、大学卒業後には正社員になった。
転機となったのは、入社から約3年後。複数の先輩社員が辞め、編集部の最古参になった。30代で編集長に就任。空が明るくなるまで残業をし、それでも終わらない仕事は家に持ち帰った。「続けていけるかな」という不安に駆られながらも、毎月欠かさず出版することを目標に続けてきた。
月刊みとは、2023年8月に創刊600号を達成した。常に将来の特集のことを考えてきただけに、過去を振り返ると「月日が経つのが思ったより早く驚きました」。
高度経済成長期の1973年1月にエンタメ情報誌「ぴあ」の水戸版を目指して発行されてから、県内のグルメやイベント情報、ゆかりの人を特集してきた。
「遠い場所の情報は憧れになる。暮らしている場所の情報をたくさん得ていた方が毎日の暮らしは豊かになる。すぐ食べられる料理、すぐ会える人。1冊あれば日々を充実させられる情報を詰め込んでいます」
過去には、職業に焦点を当てた連載も組んだ。取り上げたのは香道家、探偵、線香職人、野球審判員……。就職で東京に出る若者に、「地元でもこんなに色々な職業があり、仕事にやりがいを感じている人がいる」と伝えたかった。
「茨城に誇りを持ってもらいたい」。編集者に憧れて仕事を始めたが、いつしか原動力も変わってきた。取材を重ねるごとに、茨城を支える人や物の存在を広く伝えたいと思うようになった。
特集がマンネリ化しないように「今、何を街でよく見かける?」とアンテナを張る。
50年の歴史で2度、出版できなかった時期がある。2011年の東日本大震災の直後(4・5月の合併号に)と、20年の新型コロナ発生当初(5・6月の合併号に)だ。
震災後は前向きに復興へ向かう空気に満ちていたが、コロナ禍は休業や閉業を強いられ、先行きの見えない閉塞(へいそく)感があった。現場に行くたびに街の変貌(へんぼう)を肌で感じながら、飲食店に元気を出してもらえるように、企画を練り続けた。
誰もが情報を発信でき、無料で受け取れる時代に入り、情報を有料で買う感覚が減りつつあると感じている。「発信に責任を持っているという、無料の情報とは違う価値がある」。そう信じ、この先も月刊みとが続くことを願って、今日も取材に飛び回る。